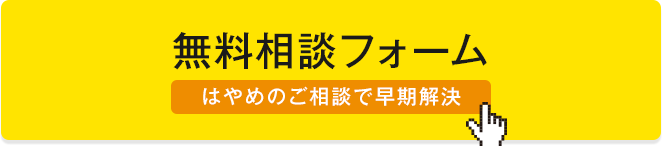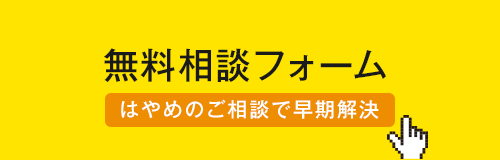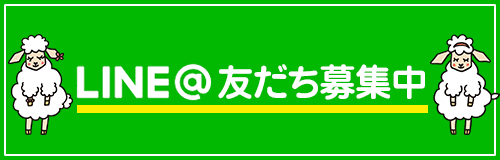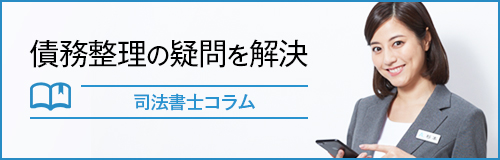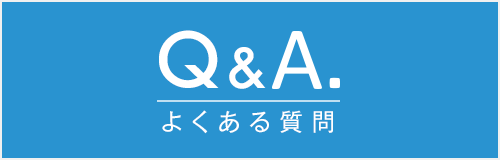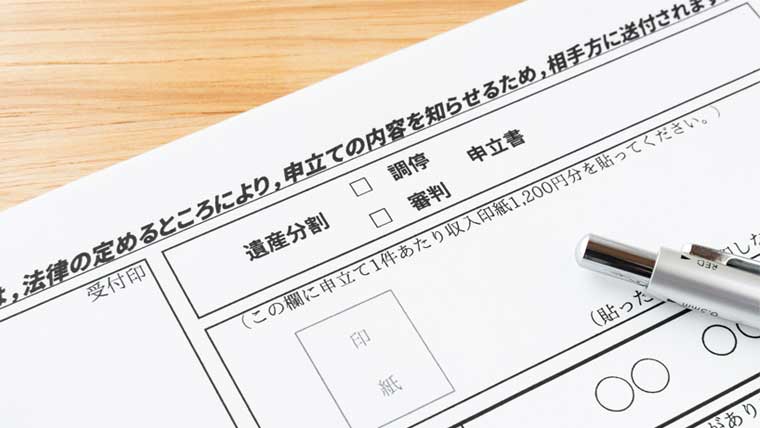2025.06.09
個人再生
個人再生ができないケースとは?その対処法を解説

債務整理のひとつに、個人再生という方法があります。
個人再生は、住宅ローンを抱える人や多額の借金を抱える人にとって有効な手段です。しかし実は、個人再生には明確な条件があり、それを満たさなかったり、手続きにミスがあると不認可となることがあります。裁判所を介して手続きを進めるため、その条件や基準を満たすことが必要です。ご自身で申し立てを行うには手間がかかりますが、そこで、弁護士や認定司法書士などの専門家に任せることによりスムーズに手続きを行うことができます。
個人再生で失敗しないためにも、この記事では、個人再生ができないケースや、その対処法について解説します。
個人再生ができないのはどんなケース?
個人再生は、借金を減額して返済計画を立てることで、経済的に立ち直るための有効な手段です。しかし、すべての人が個人再生を利用できるわけではなく、一定の条件を満たさない場合には申立てが認められないこともあります。
収入が安定していない
個人再生は、債務整理の手段の一つで、借金の一部を減額し、残りを3年以内に分割で返済するよう、再生計画を立てる制度です。この制度は、住宅ローンを抱えたままでも借金を整理できる可能性があります。しかし、個人再生にはいくつかの条件があり、その中でも特に重要なのが「収入が安定していること」です。
安定した収入が必要な理由
個人再生の基本的な要件の一つは、債務者が今後、再生計画に沿った返済ができる見込みがあることです。再生計画では、減額後の借金を3年以内に返済することが条件です。このため、安定した収入がなければ、計画的に返済を続けることが難しく、再生計画が実行不可能と見なされてしまうことがあります。
収入が安定していない場合、毎月の返済額を支払うことができるかどうかが不明確になり、再生計画が裁判所に認められない可能性が高くなります。個人再生は、債権者に対して一定額をきちんと支払う能力があることを証明するため、収入の安定性は非常に重要な要素となります。
・返済計画が立てられない:収入が不安定であれば、月々の返済額を決めることができず、具体的な返済計画を裁判所に提出することが難しくなります。
・再生計画の実行可能性が低い:収入が不安定な場合、債務者が再生計画に基づいて返済を継続することができるかどうかが不確実となり、計画が実行できるかどうかの判断材料として十分な証拠とならないため、裁判所から再生手続きを却下されることがあります。
・収入証明書が「不備」とみなされる:再生申立て時には収入証明書(給与明細書や税務署発行の所得証明書など)を提出する必要があります。これらが不安定または不十分な場合、審査が通らない可能性が高くなります。
個人再生が認められるためには、安定した収入を維持することが重要な要件です。収入が不安定な場合、再生計画が実行可能かどうかが判断され、手続きが認められないことがあります。しかし、安定した収入の見込みがあれば、その旨を裁判所に説明することで、個人再生が認められる可能性もあります。
借金総額が5000万円を超えている
個人再生は、債務者が支払不能な状態にある場合に借金減額の手段として有効ですが、すべての状況で利用できるわけではありません。その中でも重要な制限の一つが、「借金総額が5000万円を超えている場合」です。この条件に該当する場合、個人再生の手続きを進めることができません。
個人再生には、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下という制限があります。この上限を超える借金がある場合、個人再生の手続きを利用することができません。たとえば、消費者金融や銀行からの借り入れが合計で5000万円を超えている場合、個人再生は適用されません。
個人再生の目的と5000万円の制限
個人再生は、基本的に支払いが困難な借金を減額し、再生計画を立てて3~5年の期間で返済を進めることを目的としています。しかし、借金が5000万円を超えている場合、返済能力や再生計画を実現する可能性に関して、「非常に難しい」という判断になります。これにより、個人再生の適用基準として5000万円という上限が設けられています。
多額の財産がある
個人再生は、基本的には借金の減額を目指す手続きですが、「返済可能な状態」を保つことが求められます。多額の財産がある場合、裁判所は「その財産を使って返済を行うべきだ」と判断することがあります。そのため以下のようなケースでは、個人再生の申立てが却下されることがあります。
1.財産が債務額を大きく上回っている場合
借金の額に対して、非常に多くの財産を持っている場合、裁判所は「その財産を利用して借金を返済することが可能だ」と見なします。例えば、家や土地、高額な預金がある場合などです。このような場合、わざわざ個人再生を選択する理由がないとされ、申立てが却下される可能性があります。
2.不動産などの高額資産を所有している場合
住宅ローンがある場合でも、所有する不動産が高額であり、住宅ローンを除く借金の額が比較的小さい場合、裁判所はその不動産を売却して借金を返済することを求めます。これにより、個人再生が適用されないことがあります。
3.資産の処分を避ける目的で申立てを行っている場合
もし、借金の返済を免れるために、意図的に資産を隠したり、処分したりしている場合、その行為が発覚すれば、個人再生の申立てが認められません。裁判所は、誠実に返済能力を見積もった上で、手続きを進めるため、財産の隠匿や不正な処分があれば、申立ては却下されます。
多額の財産がある場合、個人再生が認められない可能性があります。財産を返済に充てることができる状況では、個人再生は適用されないことが一般的です。
申立てに必要な費用が用意できない
個人再生は、借金が膨らみ、生活が困難になった方にとって有効な債務整理の手段ですが、申立てを行うには一定の費用が必要です。費用が足りない場合、個人再生の手続きが進められない可能性があります。
個人再生の手続きには、司法書士や弁護士への報酬のほか、裁判所への申立てに必要な費用があります。具体的には以下のような費用がかかります。
・司法書士・弁護士への報酬:依頼する専門家への報酬が必要です。報酬額は依頼内容や地域によって異なりますが、一般的には数万円から十数万円程度が相場です。
・裁判所への申立て費用:個人再生を申し立てる際、裁判所に支払う費用として、予納金(おおよそ10,000円~15,000円)や、郵送費などが発生します。
・申立てに必要な書類作成費用:個人再生を進めるためには、収入証明書や家計の収支表、債権調査票などの書類が必要です。これらの書類作成にかかる費用も考慮する必要があります。
申立てを考える際には必要な金額を把握しておくことが重要です。
もし、必要な費用を用意できない場合は、分割払いの相談や、法テラスの利用を検討しましょう。法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に困難な状況にある方に対して、司法書士や弁護士費用の立て替えや支払い援助を行っています。収入や資産の状況に応じて、無料相談や費用負担の軽減が受けられる場合があります。
個人再生をしなくても返済できる
個人再生は、借金を減額し、生活を立て直すために非常に有効な手段ですが、中には、個人再生をすることなく、現在の返済方法で問題なく借金を返済できる場合もあります。次のようなケースでは、個人再生を選ばずに解決できる可能性が高いので、無理に個人再生を検討する必要はないかもしれません。
1. 収入が安定していて、返済能力がある場合
もし、現在の収入が安定しており、今後も一定の収入が見込める場合、借金を返済する余裕があるかもしれません。特に、月々の返済額が収入の中で支払える範囲に収まっている場合、個人再生のような大規模な手続きを取らなくても、通常の返済計画で十分に解決できることがあります。
2. 借金の総額が少額で、短期間で完済できる場合
借金の総額が比較的少額で、数ヶ月〜数年以内に完済できる見込みがある場合でも、個人再生を選択する必要はないかもしれません。特に、少額のクレジットカードの支払いや、消費者金融の借金などがある場合、現実的に返済可能な金額であれば、無理に手続きを進める必要はありません。
3. 債務整理をしなくても、生活費のやりくりが可能な場合
生活費のやりくりに特に問題がなく、毎月の返済額が生活に支障をきたすことなく支払える場合、個人再生を行わなくても、安定して返済が続けられるでしょう。予算管理や支出の見直し、借金の金利や返済方法の見直しなどを行うことで、より効率的に返済を進められることがあります。
4. 家族や親族からの支援が得られる場合
もしも、家族から借金の返済支援や、一時的な援助が得られる場合、個人再生をしなくても問題なく解決できることがあります。もちろん、このような場合では、家族や親族が安定している必要があり、将来的に依存し続けることなく計画的に返済を進めることが大切です。
5. 返済計画の再調整ができる場合
一部の借金について金利の低いローンに借り換えたり、返済計画を再調整することで、借金を減らさずとも返済が楽になることがあります。借金の負担を軽減し、返済可能な範囲で返済を続けることができる場合、個人再生を選択する必要はないでしょう。
個人再生は、借金の大幅な減額を求める手段ですが、必ずしもすべての人に必要な手続きではありません。収入が安定している、借金の総額が少ない、生活費のやりくりができる、家族から支援を受けられる、または借り換えなどで返済が可能な場合は、個人再生をしなくても問題なく返済を続けられることがあります。
そもそも個人再生とはどのような方法か?

個人再生は、債務整理の一つであり、裁判所を介して債務の減額を行う方法です。特に、住宅ローンを抱えている人や多額の借金で生活が困難になった人にとって、債務を整理し、生活を再建するための有効な手段となります。個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類の方法があり、実際にはほとんどの方が「小規模個人再生」を選択されます。
個人再生(小規模個人再生)の概要
個人再生は、債務者が裁判所に申し立てを行い、「再生計画」を立てることで、債務を減額し、返済可能な額に調整する手続きです。再生計画は、債務者が今後3年間で返済する金額を定め、その計画に基づいて債務を減額します。一般的には、債務額の1/5程度に減額されることが多いですが、最低でも100万円は返済することを求められます。
再生計画は、裁判所がその内容を認可することで実行に移されます。計画が認められると、債務者は新たな返済計画に基づいて、3年間で残りの債務を返済することになります。
個人再生のメリット
個人再生には、以下のような大きなメリットがあります。
・債務の大幅減額
一般的に、債務の1/5まで減額される場合が多く、支払い負担が大幅に軽減されます。減額後の残りの債務については、3年間で返済していくことになります。
・住宅資金特別条項の利用
個人再生には、住宅ローンを抱えている場合でも、自宅を手放さずに再生手続きを進めることができる「住宅資金特別条項」があります。この特例を利用することで、住宅を維持しながら債務整理を行うことが可能です。なお、住宅資金特別条項を利用するには、一定の条件があります。
・督促の停止
受任通知を裁判所に提出することにより、個人再生の手続きが進行する間に債権者からの取り立てや督促が一時的に停止されます。特に、認定司法書士や弁護士が介入することで、迅速に督促を止めることができ、精神的な負担を軽減できます。
個人再生の手続きの流れ
個人再生を進めるための基本的な流れは以下の通りです。
1.準備段階
債務者はまず、自分の債務状況を確認し、個人再生を進めるかどうかを決定します。再生計画を立てる前に、債務の総額や収入状況、支出を整理することが重要です。
2.申し立て
司法書士や弁護士のサポートを受けて、裁判所に個人再生を申し立てます。申し立てには、再生計画案や必要な書類を提出します。
3.再生計画の提出
債務者は裁判所に再生計画を提出します。この計画には、どれだけの金額を3年間で返済するか、またその根拠となる情報が盛り込まれます。
4.裁判所の審査と認可
裁判所は再生計画を審査し、問題がなければその計画を認可します。認可されると、減額された債務について返済が開始されます。
5.返済開始と完了
再生計画に基づいて、債務者は3年間で返済を行い、すべての支払いが完了すると、残りの債務が免除されます。
個人再生の注意点
個人再生には、以下の注意点もあります。
・自己破産と異なり、免責はされない
個人再生では、自己破産とは違い、すべての債務が免除されるわけではありません。返済計画が終了することで、残りの未払い額が免除されることになります。
・一部の債務は対象外
銀行などの一部の金融機関によるローンや税金など、個人再生の対象とならない債務もあります。
個人再生は、生活を立て直すための強力な手段です。住宅資金特別条項を活用すれば、住宅を守りながら債務整理が可能となります。ただし、条件や手続きには注意が必要であり、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
「給与所得者等再生要件」とは?
給与所得者等再生は、主に給与所得者など、安定した収入があり、その収入の変動幅が小さい人を対象にした個人再生の一形態です。この手続きでは、住宅ローンを除く借金の返済を原則3年以内に行うことが求められます(やむを得ない事情がある場合は最長5年まで延長可能です)。小規模個人再生と異なり、債権者の同意を得る必要がない点が特徴です。
給与所得者等再生の要件
給与所得者等再生を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 個人であること
- このままでは借金を返済できなくなるおそれがあること(支払不能のおそれ)
- 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること
- 将来にわたり継続的または反復して収入を得る見込みがあること
- 給与またはこれに類する定期的な収入があり、その収入の変動幅が小さいこと(過去2年間の年収の変動が20%未満など)
- 過去7年以内に給与所得者等再生、自己破産、ハードシップ免責をしていないこと
- 再生手続開始の申立て棄却事由(民事再生法25条各号)がないこと
- 申立て時に給与所得者等再生を希望する旨を申し述べていること
個人事業主であっても、収入の変動幅が小さい場合には利用可能ですが、一般的には小規模個人再生の利用が多いです(住宅ローン調整が必要な場合は小規模個人再生を要する)。
給与所得者等再生の特徴とメリット
給与所得者等再生を利用することで得られるメリットは以下の通りです。
- 住宅ローンを除いた借金が大幅に減額される
- 債権者の同意が不要で、再生計画が早期に確定する
- 返済額が減り、生活の安定が図れる
返済額は、以下の3つの基準から最も高い金額が採用されます。
1.最低弁済額:債務総額の1/20(100万円未満の場合は100万円)
2.清算価値:債務者の全財産をすべて処分した場合の価値
3.可処分所得の2年分:債務者の収入から税金や社会保険料、最低限度の生活費(生活保護基準等に基づく)を差し引いた後の金額の2年分
給与所得者等再生では、この3つのうち最も高い金額を3年(特別な事情がある場合は最長5年)で返済する必要があります。
給与所得者等再生の申立て手続き
給与所得者等再生の申立ては、専門家である司法書士や弁護士を通じて行います。この手続きでは住宅資金特別条項は利用できず、住宅ローンを含む場合は小規模個人再生が必要です。申立てには、以下の書類が必要です。
- 収入を証明する書類(給与明細、源泉徴収票など)
- 借金の詳細を記載した債権調査票
- 家計の収支表
- 事業所得がある場合は、事業に関する証明書類
これらの書類をもとに、再生計画を立て、裁判所に申立てを行います。
給与所得者等再生は、安定した収入があり、その変動幅が小さい方にとって、借金の減額を受けつつ、生活を再建するための有効な手段です。しかし、申立てには細かな条件を満たす必要があるため、事前に専門家と十分に相談し、申立てを行うことが重要です。
個人再生が認められるには条件がある
個人再生を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件に基づいて、裁判所が申立てを受理するかどうかを判断します。
まず、再生計画に基づいた弁済が可能であることが条件となります。具体的には、再生計画に沿った返済を行うための十分な収入が必要です。また、将来的に安定した収入源を確保できる見込みがあることも、大切な条件です。
さらに、個人再生を申立てるには、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であることが条件です。この上限を超える場合、個人再生は認められません。
個人再生は、借金の全額が免除されるわけではなく、借金の減額措置です。減額後の借金は原則として3年以内に返済しなければならず、そのためには、安定した収入を維持し、計画的に返済を進めることが必要です。裁判所は、提出された書類をもとに、再生計画に沿った返済が可能かどうかを判断します。
・収入証明書類:月々の収入や所得を証明する書類(給与明細や税務署の発行する証明書など)。
・家計の収支表:収入と支出のバランスを示す表。
・財産証明書類:所有する財産(不動産や預金、車両など)の詳細を記載した証明書。
・債権調査票:借金の詳細(債権者名、金額、利息など)を記載した書類。
・再生計画案:返済計画や支払い方法を記載した計画書。
これらの書類を裁判所が慎重に精査し、再生計画に沿った返済が実行可能かどうかを判断します。もし、提出された書類や計画内容に基づいて、明らかに再生計画の実行が難しいと判断された場合、個人再生の申立ては認められません。再生計画が現実的でない場合、裁判所は申立てを却下することがあります。
個人再生が不認可になるケースとは?

個人再生は、債務整理の中でも住宅を守りながら借金を減額できる有効な手段ですが、申立てが不認可になるケースもあります。ここでは、個人再生が不認可になる原因と、その対処法を解説します。
[書類の提出期限を守れない]
個人再生の申立をする際には、裁判所に対して必要な書類を提出しなければなりません。これらの書類には、財産や収入の証明書類、家計の収支表、再生計画案などがあります。裁判所には提出期限が設定されており、この期限を守らないと、申立てが認められなくなります。
対処法
書類提出に必要な時間を事前に確認し、余裕を持って準備することが大切です。必要な書類をあらかじめ整理し、早めに専門家(司法書士や弁護士)と協力して進めることが失敗を防ぐために重要です。
[再生計画の実行が不可能と判断される]
再生計画は、借金の減額後、どのように返済していくかを示す重要な計画です。裁判所は、提出された再生計画が現実的で実行可能かどうかを厳しく審査します。返済額や返済期間が過大であったり、支払い能力を超えていると判断されると、再生計画は不認可となります。
対処法
返済額が無理なく実行できるかどうか、現実的な計画を立てる必要があります。専門家と一緒に計画を立て、現実的な返済額とスケジュールを設定することが重要です。自分の生活費や必要な支出をしっかりと考慮し、返済額を設定することで実行可能な計画を作成しましょう。
[再生計画案に不正がある]
再生計画案に記載された財産や現金について虚偽の申告をしたり、隠蔽したりすることが発覚した場合、個人再生は即刻不認可となります。これは、裁判所が誠実な手続きを進めることを求めているためです。再生計画案に不正があると、法的な問題が生じ、個人再生そのものが認められません。
対処法
財産や収入については正直に報告し、虚偽や隠蔽は絶対に避けるようにしましょう。裁判所に提出する書類は、全て正確かつ真実に基づいて作成することが最も大切です。不正行為を防ぐため、申告すべき内容については専門家としっかりと相談し、疑問点があれば確認してから提出するようにしましょう。
[特定の債権者にだけ返済した場合]
個人再生を申立てた後、特定の債権者にだけ返済を行うことは認められません。個人再生では、すべての債権者を平等に扱い、再生計画に従って返済する義務があります。特定の債権者にのみ返済を行うと、他の債権者から不満が出ることはもちろん、法的に問題となり、個人再生が不認可になるリスクがあります。
対処法
すべての債権者に対して平等に対応することが必要です。債務整理を進める際には、再生計画に基づいた返済を行い、債権者間での不公平感を避けるようにしましょう。債権者への返済は、計画に従い、公平に分配することが求められます。返済の順番や金額について専門家に相談し、適切な対応をすることが重要です。
個人再生は、借金を減額し、生活を再建するための手段ですが、一定の条件を満たさない場合や不正があった場合には不認可になることがあります。書類の提出期限を守り、実行可能な再生計画を作成し、すべての債権者を平等に扱うことが重要です。
まとめ

個人再生は、借金が多くても、住宅を手放さずに返済を続けることができる救済措置として非常に有効です。しかし、すべてのケースで必ずしも成功するわけではなく、場合によっては失敗に終わることもあります。個人再生で失敗する理由にはいくつかの要因が考えられますが、それに対する対処法も存在します。
1. 収入が不安定な場合
個人再生を申し立てる際、裁判所は再生計画に基づいて3年間での返済計画を立てます。これには、安定した収入が不可欠です。収入が不安定な場合や、再生計画に基づいた返済が現実的に難しいと判断されると、個人再生が認められないことがあります。
対処法
再生計画を立てる前に、安定した収入を得られるかどうかを事前に考慮することが重要です。もし収入が安定しない場合には、再生計画を修正するか、他の債務整理方法(自己破産や任意整理など)を検討する必要があります。収入が不安定でも、家庭の支出を見直し、無駄を減らすことで返済能力を高める努力が必要です。
2. 借金の総額が5000万円を超える場合
個人再生の申立てをするには、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下である必要があります。この金額を超える借金がある場合、個人再生は認められません。
対処法
5000万円以上の借金がある場合には、個人再生の代わりに自己破産を検討する必要があります。自己破産には借金を全額免除するメリットもありますが、その後の生活に制約がかかる点を理解した上で判断することが重要です。もし少額の借金を複数の業者から借りている場合、任意整理などで整理することも選択肢として考えられます。
3. 虚偽の申告や隠蔽がある場合
申立て時に、財産や収入の情報について虚偽の申告したり、隠蔽したりすることは絶対に避けなければなりません。もし裁判所が虚偽や不正行為を発見した場合、個人再生の申し立ては却下されます。
対処法
申立て前に、収入や財産、借金の状況を正確に整理し、正直に申告することが最も大切です。虚偽の申告や隠蔽をしても、最終的に不利な結果となり、手続きがうまく進まないだけでなく、法的な問題に発展する恐れもあります。
4. 再生計画案が不十分な場合
再生計画が現実的でなかったり、返済の見通しが不明確な場合、裁判所が計画を認めないことがあります。再生計画案には、返済期間や金額を明確に示し、具体的な返済方法を立てることが求められます。
対処法
再生計画案を立てる際は、専門家である司法書士や弁護士と一緒に進めることをお勧めします。実行可能な返済計画を作成し、債権者と協議の上で調整を行うことが必要です。
5. 過去の破産歴がある場合
過去に自己破産をしたことがある場合、その後の個人再生の申し立てが難しくなることがあります。特に短期間に複数回の破産歴がある場合、信用を回復するためには時間がかかります。
対処法
過去の破産歴がある場合でも、個人再生が可能な場合がありますが、その場合は専門家に相談し、計画的に進めることが必要です。場合によっては、自己破産を再度選択することも検討する必要があります。
個人再生は、借金問題を解決するための有効な方法ですが、いくつかの条件を満たす必要があります。収入の安定性や再生計画の実現性、借金額などがうまく整わないと、個人再生の手続きが、うまくいかないこともあります。
裁判所を介して行う個人再生は、手続きが非常に複雑です。提出書類の作成も、ご自身で行う場合、手続きの経験がない一般の方には、かなり難易度が高いものになります。個人再生を行うには専門家のサポートが必要となってきます。個人再生のご相談は経験と実績の豊富なアヴァンス法務事務所にご相談ください。個人再生のみならず、他の債務整理の方法や、過払い金の請求など、メリット・デメリットをそれぞれ考慮した上で、アドバイスさせていただきます。電話やメールで無料相談を受付しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。