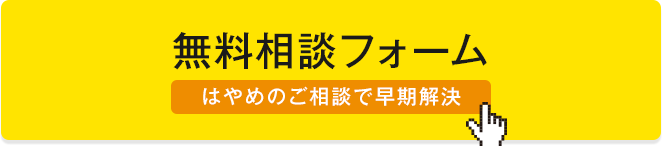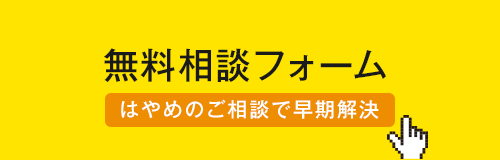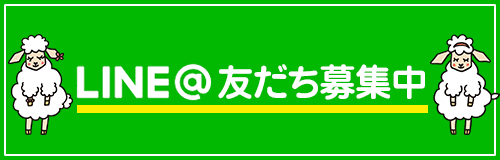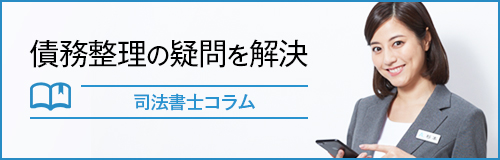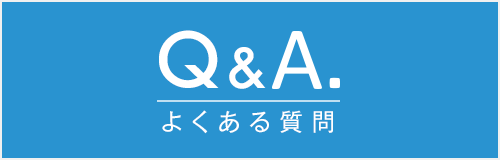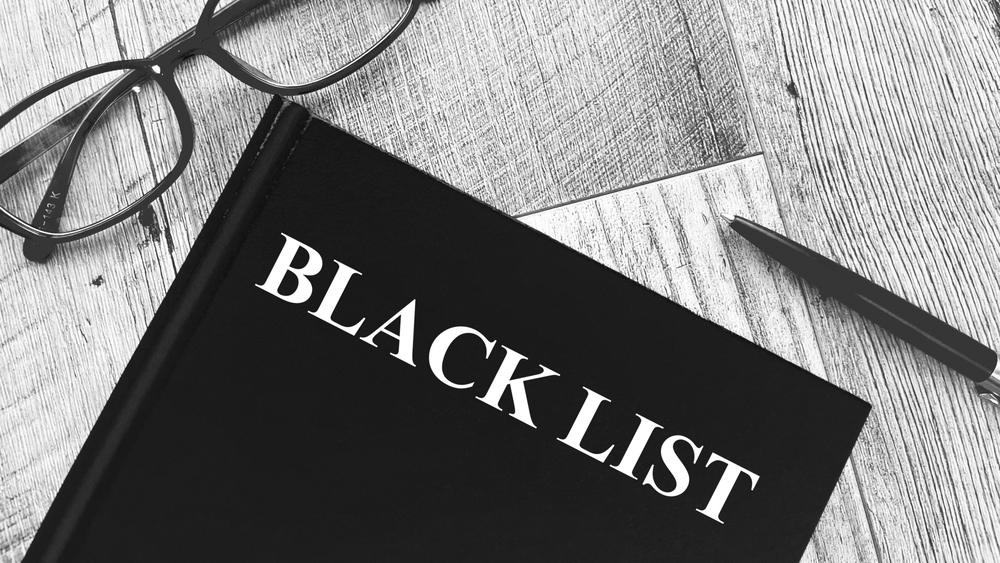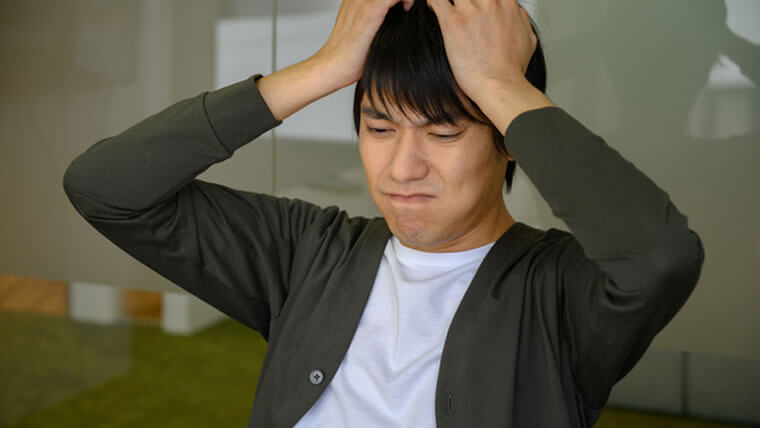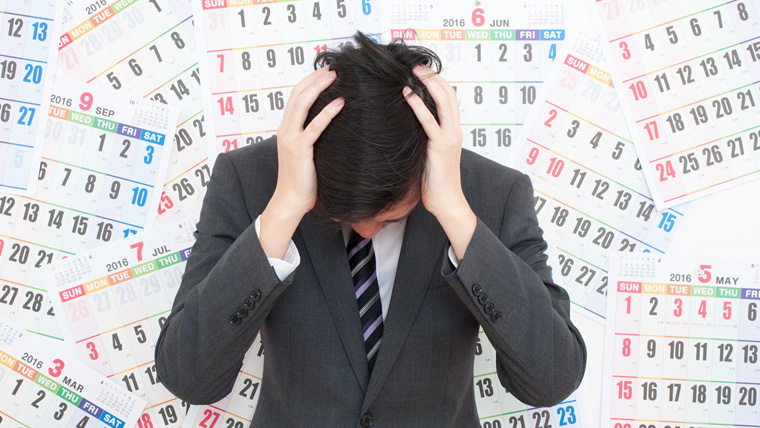2025.10.20
任意整理
任意整理(債務整理)後の追加介入とは?支払ができない時の対処法を解説

任意整理をしたのに、「返済が続けられなくなってしまった」「また支払えずに遅れてしまった」──そんな不安を抱えていませんか?
任意整理後に返済が滞ると、再び債権者からの催促や一括請求を受ける可能性があります。この状況を放置すると、せっかく整えた返済計画が無効になり、法的手続き(差し押さえなど)に発展するリスクも否定できません。
こうしたトラブルに直面した場合は、「追加介入」と呼ばれる再交渉の手続きによって、返済計画を見直すことが可能です。この記事では、任意整理後に返済が苦しくなってしまった時に検討するべき「追加介入」について解説します。
任意整理の追加介入とは?

任意整理の追加介入とは、すでに任意整理手続きを開始した後で、当初は対象外にしていた債権者を、後から新たに追加する手続きのことです。「一度始めた任意整理は、もう変更できない」そう思っていませんか?実は、柔軟に対応できるケースも多いものです。
任意整理における追加介入の定義と注意点
追加介入とは、あなたの返済状況や生活環境の変化に合わせて、最初の任意整理計画に新たな債権者を含める手続きです。たとえば、任意整理後に残った借入先の返済が厳しくなったり、生活費が足りず、また新たに借金をしてしまったり…そんな時に検討されるものです。
ただし、追加介入はじっくり考える必要があります。すでに和解した債権者との関係に影響が出る可能性もあるからです。追加介入によって全体の返済計画が変われば、既存の和解条件の見直しが必要になることも考えられます。また、新たに追加する借金の金額や返済条件によっては、かえって返済負担が重くなってしまうケースも否定できません。慎重な判断が求められます。
さらに大切なのは、追加介入のタイミングです。既存の任意整理が順調に進んでいる間に対応できれば比較的スムーズに進むでしょう。しかし、すでに返済が滞ってしまっている状況では、債権者からの信頼を損なう可能性も出てきます。任意整理後の対応は「期限利益の喪失」により一括での返済を求められることもあり、そうなった場合には早急な対応が必要です。そのため、追加介入を検討する際は、今の返済状況と今後の収入見込みを総合的に判断することが不可欠です。
最初の任意整理手続きとの違いは?
最初の任意整理と追加介入では、いくつか違いがあります。一番大きな点は、すでに任意整理の手続きが進行中である、という前提です。
初めての任意整理では、すべての借入先を一度に把握し、全体的な返済計画を立てられます。一方、追加介入では、既存の返済計画とのバランスを取りながら、新しい債権者を含めた計画を再構築しなければなりません。これは単なる追加ではなく、全体のバランスを考える複雑な調整作業になります。
また、債権者との交渉にも違いが見られます。初回の任意整理では「初めての債務整理」という状況で交渉を進められますが、追加介入では「すでに他の債権者と和解している」という事実があります。これが交渉にどう影響するかは、債権者によって様々です。理解を示してくれるところもあれば、より厳しい条件を出してくる債権者もいるかもしれません。
手続きの複雑さも異なります。追加介入では、既存の和解契約書の内容確認、現在の返済状況の整理、新旧の債務を含めた返済能力の再評価など、初めての時よりも多くの作業が必要です。そのため、専門家へ依頼する費用も、初回とは異なる料金体系が適用されるのが一般的です。
追加介入ができる条件とタイミング
追加介入が可能かどうかは、条件とタイミングが関係してきます。まず、最も重要なのは、現在進行中の任意整理が順調であることです。すでに既存の借入先への返済が滞ってしまっている状況では、新たな債権者を追加するのは現実的ではない、という側面があります。
収入の安定性も大切な条件です。追加介入で返済総額が増える分、それに見合った安定した収入があることが前提となります。一般的には、住宅ローンや生活費を除いた、自由に使えるお金の範囲内で、すべての借金の返済が可能であることが求められるでしょう。
タイミングについては、既存の任意整理を開始してから3〜6ヶ月以内が理想的と言われています。この時期であれば、全体の返済計画の見直しも比較的スムーズに進めやすいはずです。逆に、既存の任意整理が長期間経過していると、追加介入が難しくなる傾向にあるため、注意が必要です。
また、追加したい借入先(債権者)の種類や借金(債務額)も重要です。比較的少額の借金や、交渉に応じやすい債権者であれば追加しやすいでしょう。一方で、高額な借金や厳しい条件を出してくる可能性が高い債権者の場合は、より慎重な判断が求められます。
追加介入を考えているなら、今の状況を専門家に詳しく相談することが何よりも大切です。任意整理後に返済が苦しいと感じ始めたら、早めに相談されることをおすすめします。
任意整理で追加介入するメリット

任意整理をすでに開始している状況でも、当初対象外にしていた借入先を後から追加することは可能です。任意整理をされた方が、最初の任意整理では一部の債権者だけを対象としたものの、その後状況が変わり、追加介入を検討されています。
追加介入には、今の返済負担を大きく減らせる、という明確なメリットがあります。ただし、検討する際は、現在の収入と支出、そして今後の返済計画を総合的に判断することが大切です。
月々の返済負担の軽減
追加介入の最も大きなメリットは、なんといっても月々の返済額が大幅に減ることです。任意整理は、一般的に3年から5年の分割払いで和解することが多いもの。毎月の返済負担を、今の半分以下に抑えることも可能になります。
たとえば、月収30万円の方が任意整理で月8万円の返済が月4万円に減額されたとします。当初は、残り4万円の軽減分で、対象外にした債権者への月3万円の返済を続けられると考えていたかもしれません。しかし実際には、生活費が上がったり、急な出費があったりして、この3万円を捻出するのが難しくなるケースも考えられます。
このような状況であれば、対象外だった債権者も任意整理に含める追加介入を検討する価値があります。無理に返済を続けて生活が破綻したり、新たな借金に手を出したりするリスクを避けられるからです。追加介入によって、全体の返済計画をさらに現実的なものに再構築できる可能性も高くなります。
また、返済額が減れば、返済遅延のリスクも大幅に下がります。無理のない返済計画で、長期的に安定した返済を続けられ、結果として債務整理の成功にもつながるはずです。
利息カットによる総返済額の削減
任意整理の追加介入では、将来利息のカットが期待できることも、見逃せません。これは月々の負担を軽くするだけでなく、返済総額を大幅に減らすことにもつながる、大切なメリットです。
消費者金融やクレジットカードの利息は、年率15%から18%程度が一般的です。しかし、任意整理によって将来利息がカットされれば、元本だけを返済すればよくなります。たとえば、100万円の借入に年率18%の利息が付いていた場合、5年間で支払う利息は約50万円にものぼります。これがカットされるのですから、その負担はなくなるわけです。
さらに、遅延損害金についても交渉次第で免除される場合があります。返済が滞っていた期間の遅延損害金は高額になることも少なくありませんから、これがカットされれば、返済総額は大きく圧縮されます。追加介入によって、当初考えていた以上に債務整理の効果を実感できるはずです。
複数ある借金の一本化で管理が楽になる
追加介入のもう一つのメリットは、複数の借入先を同時に任意整理することで、返済管理が格段に楽になることです。現在任意整理中の借入先と、新たに追加する借入先をまとめて、わかりやすい返済スケジュールを組むことができます。
複数の借入先があると、それぞれ返済日も返済額も支払い方法もバラバラで、うっかり忘れてしまうリスクも考えられます。でそこで、任意整理で返済を一本化すれば、毎月決まった日に決まった金額を支払うだけでよくなり、シンプルな管理が可能になります。
また、弁護士や司法書士があなたの窓口となることで、債権者とのやり取りも一本化されます。返済に関する相談や変更手続きも専門家を通して行えるため、直接債権者と交渉する精神的な負担からも解放されるはずです。返済の管理を改善することは、長期的な返済を続ける上で非常に大切になります。
追加介入を検討されるなら、今の返済状況や今後の収入見込みについて、専門家と詳しく相談することが大切です。
追加介入のデメリット
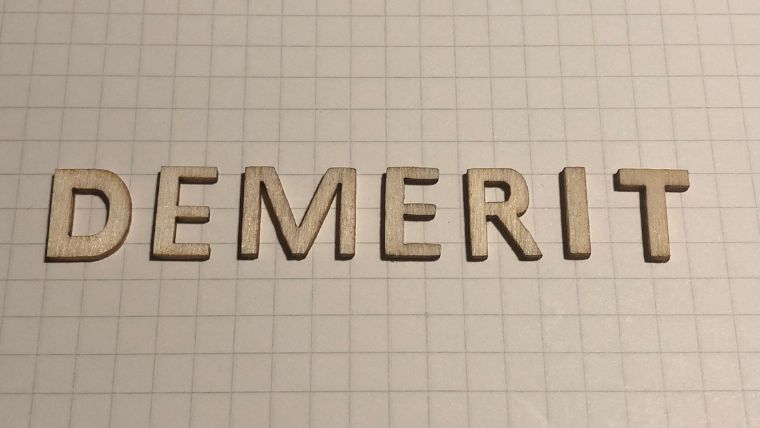
任意整理を開始した後に、新たな債権者を手続きに含める「追加介入」には、いくつか知っておくべきデメリットがあるのは確かです。すでに任意整理を始めた後で、当初対象外にしていた借入先の返済も厳しくなってきた…そんな状況で追加介入を検討する際、やはり気になるのは「デメリット」ではないでしょうか?以下、解説していきます。
追加の弁護士・司法書士費用と手続き期間
追加介入を行う際に、まず直接影響するのが費用です。新たに手続きに加える債権者1社につき、通常2万円〜5万円程度の追加費用が発生するのが一般的でしょう。これは、債権者への受任通知送付、借金状況の調査、和解交渉といった一連の手続きを改めて行う必要があるからです。
すでに月々の返済と専門家への分割払いで家計が厳しい場合、この追加費用が大きな負担となることも考えられます。特に、複数の債権者を一度に追加するなら、費用は債権者の数に応じて増えていきますから、事前の資金計画がとても重要です。
手続き期間も、新たに債権調査から和解交渉まで行うため、通常2〜4ヶ月程度かかると考えてください。この間、追加対象の債権者からの督促は止まりますが、和解が成立するまでは返済も一時停止となるケースが多く、その間に利息や遅延損害金が発生し続ける可能性も考慮しておく必要があるでしょう。
また、既存の任意整理手続きがほぼ完了している段階での追加介入は、専門家の業務状況や優先順位によっては、通常よりも時間がかかることもあります。担当者との連絡や相談が増える分、精神的な負担も考慮しておきたいところです。
既存の和解内容への影響と対処法
追加介入で特に注意したいのが、すでに成立している和解内容への影響です。現在返済中の債権者からすれば、あなたの総返済負担が増えることで、「これまでの和解条件をちゃんと履行できるのか?」と疑問を抱かせる要因となる可能性があります。
たとえば、月々5万円の返済で3社と和解が成立していた状況で、新たに2社を追加し、総返済額が7万円になったケースを考えてみましょう。既存の債権者が「本当に返済を継続できるのか」と不安に感じることもあるかもしれません。特に、過去に返済遅延があったり、収入状況に変化があったりする場合は、より慎重な対応が求められるでしょう。
対処法としては、追加介入の前に、現在の家計状況と追加後の返済計画を専門家と一緒にじっくり検討し、無理のない返済プランを作成することです。また、既存の債権者に対しては、必要に応じて現在の状況を説明したり、返済の意思を伝えたりと、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
場合によっては、既存の和解条件の見直しが必要になることもありますが、これは債権者の合意があって初めて可能になることです。必ずしも期待通りの結果が得られるとは限りません。追加介入の判断は慎重に行う必要があるでしょう。
債権者との関係悪化の可能性
追加介入によって、債権者との関係が悪化するリスクも考慮しておきましょう。特に、もし最初から任意整理の対象にしていれば、もっと有利な条件で和解できたかもしれない債権者の場合、「なぜ最初から含めなかったのだろう?」と不信感を抱かれることもあります。
消費者金融やクレジットカード会社などの債権者は、あなたの返済状況や手続きの経緯を詳細に記録しています。途中での追加介入は、「返済計画が甘かったのではないか」「初期の情報開示が不十分だったのでは」という印象を与えてしまうかもしれません。その結果、利息のカットや返済期間の延長といった和解条件が、当初から含めていた場合より不利になることも考えられます。
また、同じグループ内の金融機関や、情報共有している債権者の場合、ある一社での対応が、他の会社での交渉にも影響を与えることがあります。たとえば、A社で厳しい対応を受けたことで、関連するB社での交渉も難しくなる可能性も出てきます。
ただし、こうしたリスクがあるからといって、今の返済が困難な状況をそのままにしておくのは得策ではありません。延滞が長引けば、さらに深刻な問題に発展する可能性があるからです。大切なのは、今の状況を正直に専門家に相談し、最適なタイミングと方法で対処することです。
任意整理で追加介入を検討すべきケース

任意整理は、たとえ開始した後であっても、状況の変化や新たな事情があれば、追加で債権者を手続きに含めることが可能です。ただし、どのようなケースで追加介入を検討すべきなのか、その判断基準を知っておくことが大切です。追加介入は、単に「返済が苦しいから」という理由だけでなく、総合的な返済計画への影響や、将来的な家計の安定性まで考慮して決断する必要があります。
対象外だった債権者への返済が困難な場合
任意整理で一部の債権者だけを対象とした場合、除外した借入先への返済はこれまで通り続ける必要があります。しかし、手続き開始後に家計状況が変わったり、当初の予定よりも返済負担が重くなったりすることも考えられます。
ただし、追加介入には債権者との再交渉が必要となり、時間も費用もかかる点は理解しておきたいですね。専門家と相談し、今の返済能力と将来的な収入・支出の見込みを慎重に検討することが大切になります。
除外した借金の利息・負担が重くなった場合
任意整理の対象外とした借金も、利息や遅延損害金は通常通り発生し続けます。特に消費者金融やクレジットカードのリボ払いなど、金利の高い借金は、元本がなかなか減らず、利息の負担ばかりが膨らんでいくことがあります。
例として、年利18%のクレジットカードの借金50万円を対象外にした場合、月々の最低返済額(通常1万円程度)では、利息だけで月7,500円ほど発生します。つまり、元本は月2,500円程度しか減らないということになります。このペースでは完済まで非常に長い期間がかかるだけでなく、総返済額も大幅に増えてしまうでしょう。
さらに、返済が遅れれば遅延損害金(通常年利20%程度)が加算され、負担はさらに重くなってしまいます。このような状況であれば、当初の判断を見直し、追加介入を検討することが合理的な選択肢となるはずです。
任意整理に含めれば、利息のカットや減額交渉が可能となり、元本だけの分割返済や大幅な減額が実現できるかもしれません。月々の負担軽減だけでなく、完済までの期間短縮、そして総返済額の削減効果も期待できます。
新たな借入先が発覚した場合
任意整理の手続きを進める中で、当初把握していなかった借入先が発覚するケースは、決して珍しくありません。長年にわたって複数の金融機関から借金をしていると、一部を見落としてしまうことや、家族名義の借金が発覚することもあるでしょう。
たとえば、携帯電話の分割払いが信用情報機関に登録されていることを忘れていた、過去に使ったカードローンに少額の残債があった、というケースも見られます。また、ご自身が保証人となっている借金について、主たる債務者の返済が滞り、保証債務の履行を求められる、そんなケースも考えられます。
このように新たな借金が発覚した場合は、それらも含めて総合的な返済計画の見直しが必要になります。たとえ少額であっても、複数の債権者に個別に対応するのは手間がかかるだけでなく、管理も煩雑になりがちです。精神的な負担も、決して軽視できるものではありません。
追加介入によって、新たに発覚した借金も含めて一括管理できれば、返済スケジュールを統一し、管理も簡素化できます。また、借入先が多い場合は、一部だけを任意整理の対象にするよりも、まとめて整理する方が交渉上有利になることもあるでしょう。
大切なのは、新たな借金が発覚した時点で、すぐに専門家に相談し、現在進行中の任意整理への影響を評価してもらうことです。そのままにして状況が悪化する前に、適切な対応策を検討することが重要です。
任意整理で追加介入を行う具体的な手続きの方法

任意整理の追加介入とは、現在の手続きに新たな債権者を加えることです。追加介入が必要になる理由は様々でしょう。当初は返済可能だと思っていた借入先でも、生活状況の変化や他の債務整理による収支バランスの変動で、予想以上に負担が重くなることは少なくありません。こうした状況で大切なのは、早めに専門家に相談することです。返済が困難になってから時間が経つほど、債権者との交渉は難しくなる傾向にあります。
専門家への相談から手続き開始までの流れ
追加介入を検討する際は、まず現在任意整理を依頼している専門家に相談することから始めます。すでにあなたの状況を把握している専門家なら、スムーズに対応してくれるはずです。相談時には、追加対象となる借入先の詳しい情報、現在の返済状況、収入や支出の変化などを整理して伝えてください。
専門家は相談内容をもとに、追加介入が実現可能かどうかを検討します。この時大切になるのが、現在の返済能力を改めて評価することです。既存の任意整理による月々の返済額に、新たな借入先への返済額が加わっても、本当に継続できる計画が立てられるか、慎重に判断します。場合によっては、既存の和解内容の見直しが必要になることもあるでしょう。
手続き開始が決まれば、専門家が追加対象の債権者に受任通知を送付します。これにより、その債権者からの直接的な取り立てや催促は停止されますので、安心してください。受任通知の送付と同時に借金状況の調査も行われ、正確な借入残高や利息の計算が実施されます。特に長期間の借金がある場合は、利息制限法に基づく引き直し計算によって、過払い金が返還されたり、返済すべき金額が大幅に減額される可能性も期待できます。
手続きを進める際に注意すべき点は、既存の任意整理への影響です。追加介入で返済総額が増加すれば、月々の返済額も変わるかもしれません。専門家は、全体のバランスを考慮し、無理のない返済計画を立ててくれます。また、追加介入のタイミングによっては、既存の債権者との再交渉が必要になることもあるため、総合的な戦略が重要です。
追加対象の債権者との交渉
借金状況の調査が完了したら、追加対象の債権者との和解交渉が始まります。ただし、債権者によっては任意整理に対する考え方が異なるため、個別の対応が必要になるケースもあります。
交渉の主なポイントは、将来利息のカット、遅延損害金の減額、そして返済期間の設定です。多くの場合、将来利息はカットされ、元本だけを3年から5年程度の期間で分割返済するという条件で和解が成立します。ただし、借入期間が短い場合や、債権者の方針によっては、一部利息の支払いを求められることもあります。
交渉を有利に進めるには、返済の意思と能力を明確に示すことが重要です。専門家は、あなたの収入証明書や家計簿などの資料をもとに、現実的な返済計画を提示してくれるでしょう。すでに他の債権者と和解が成立している事実は、返済の意思を示す有効な材料にもなります。
債権者との交渉では、時には厳しい条件を提示されることもあるかもしれません。しかし、専門家は豊富な経験と実績を活かし、あなたにとって最も有利な条件を引き出すよう努力してくれるはずです。場合によっては、一括返済での大幅な減額や、返済期間の延長など、柔軟な提案を行うこともあるでしょう。
返済計画の再策定と合意までのポイント
追加介入によって新たな債権者との和解が成立したら、全体の返済計画を立て直す必要があります。これは、単純に返済額を足し算するだけではありません。あなたの収入や生活費とのバランスを考慮した、総合的な計画です。専門家が、無理なく継続できる現実的な計画を立案してくれるでしょう。
返済計画を立てる際には、返済の優先順位も大切な要素です。通常は、担保がある借金や、返済を怠った場合の影響が大きい借金を優先的に返済していきます。また、各債権者への返済開始時期を調整することで、月々の負担をわかりやすくすることも可能になります。
合意に至るまでのポイントの一つは、返済開始時期の調整です。追加介入の手続きには一定の時間がかかりますから、既存の任意整理による返済と、新たな債権者への返済のタイミングがずれることもあります。この期間をうまく利用して、返済資金の準備や家計の見直しを行うことも可能です。
最終的な合意が成立したら、和解契約書が作成されます。この和解契約書には、返済金額、返済期間、返済方法など、詳しい条件が記載されています。和解書は法的な拘束力を持つため、内容をしっかり確認し、疑問点があれば必ず専門家に確認するようにしてください。
追加介入による任意整理は、適切な手続きを踏めば十分に実現可能です。ただし、個々の状況によって最適な解決方法は異なります。もし今の返済状況に不安を感じているなら、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。
追加介入できない場合の任意整理以外の選択肢

任意整理で一部の債権者を対象外にしていた場合、後からその借入先だけを追加で任意整理するのは、すでに手続きを終えた債権者との公平性から難しいケースも多いのが実情です。
まず大切なのは、今の返済能力と借金総額を正確に把握することです。任意整理後の返済分と、対象外の借金の合計が、収入に対してどれくらいの負担になっているのかを客観的に見ることで、最適な解決策が見えてくるでしょう。
個人再生への切り替えメリット・注意点
個人再生は、任意整理よりも大幅な借金減額が期待できる手続きです。借金総額に応じて、債務を5分の1から10分の1程度まで圧縮できる可能性があり、任意整理では解決できなかった借金も含めて、全体的な見直しができます。
個人再生
・債務減額効果:借金の元金をおよそ5分の1~10分の1に減額できます(最低100万円)。
・財産の扱い:住宅ローン特則を利用すれば、持ち家や車を残せる場合があります。
・手続きと期間:裁判所を通す必要があり、任意整理より複雑。完了まで半年~1年程度かかることが多いです。
・資格制限:特に制限はありません。
・信用情報への影響:事故情報として約5~7年記録されます。(いわゆる「ブラックリスト」)
・官報への掲載:あり(一般の人が目にする機会は少ないです)。
・対象となる借金:原則すべての借金が対象ですが、税金など一部は免除されません。
個人再生の大きな特徴は、住宅ローン特則を利用できることです。マイホームを手放すことなく、その他の借金を大幅に減額できるため、ご家族のいる方にとっては非常に魅力的な選択肢となるでしょう。また、任意整理とは異なり、すべての債権者に対して平等に手続きが行われますので、一部の債権者だけが不利益を被る心配もありません。
ただし、個人再生には厳格な条件があります。継続的な収入があることが前提で、サラリーマンなど給与所得者であれば比較的要件を満たしやすいです。しかし、自営業者の場合は収入の安定性を証明する必要があります。また、住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下でなければならず、手続きも任意整理より複雑で、期間も長くかかります。
裁判所を通じた手続きのため、官報に氏名が掲載される点も理解しておく必要があります。とはいえ、一般の方が官報を日常的に確認することはほとんどないため、実際に周囲に知られるリスクは低いと言えるでしょう。
自己破産を検討する際のポイント
自己破産は、借金をゼロにできる最も強力な債務整理手続きです。しかし同時に、最も慎重に検討すべき選択肢でもあります。今の収入と支出の状況が、将来的に見ても改善の見込みがなく、任意整理や個人再生での解決がどうしても難しい場合に選択される手続きです。
自己破産
・債務減額効果:すべての借金が免除され、返済義務がゼロになります。
・財産の扱い:自宅や高額な車など、一定以上の財産は処分の対象になります。
・手続きと期間:裁判所での手続きが必要で、最も複雑。期間は半年~1年ほどかかることが一般的です。
・資格制限:手続き中は警備員や士業など、一部の職業に就けない制限があります。
・信用情報への影響:事故情報として約5~10年記録されます。
・官報への掲載:あり(一般の人が目にする機会は少ないです)。
・対象となる借金:原則すべての借金が対象ですが、税金や一部の罰金などは免除されません。
自己破産のメリットは、何よりも免責により借金から完全に解放されることでしょう。任意整理のように3〜5年間の返済期間を設ける必要がなく、手続き完了後は経済的に新しいスタートを切ることができます。また、生活に必要最小限の財産は手元に残せるため、完全に無一文になるわけではありませんから、ご安心ください。
一方で、注意点も多くあります。持ち家や価値の高い車などの財産は処分の対象で失うことになる可能性が高く、一定期間は新たな借入やクレジットカードの作成が難しくなります。また、手続き中は警備員や保険外交員など、一部の職業に就くことができないという制限もあります。
特に大切なのは、ご家族への影響を十分に考慮することです。配偶者名義の財産には影響しませんが、ご家族が保証人になっている借金がある場合は、迷惑がかかる可能性があり、その影響を慎重に検討しなければなりません。破産手続きはご家族の理解と協力があってこそ成功するものですから、事前の相談は欠かせないものです。
家計見直しによる現状維持の方法
債務整理以外の方法として、家計を根本的に見直して、今の返済を続ける道も考えられます。これは一時的な資金繰りの改善ではなく、継続して家計を改善していくためのアプローチです。
まず大切なのは、収入と支出を詳しく把握することです。任意整理開始から現在までの家計状況の変化を月単位で分析し、どの項目で支出が増えているのかを明確にしてみましょう。意外と、コンビニでの少額支出や定額制のサービス料金など、無意識のうちに積み重なっている支出が見つかることも多いものです。
支出削減の優先順位をつけることも大切です。まずは固定費から見直しを始めてみましょう。携帯電話料金、保険料、光熱費等、毎月決まって発生する支出の見直しは効果が大きく、一度見直せば継続的に節約効果が期待できます。通信費なら格安SIMへの切り替え、保険なら必要保障額の再計算など、具体的な行動に移しやすい項目から始めるのがコツです。
収入増加の可能性も検討してみてください。副業が可能な職場環境なら、週末や平日夜間を活用して収入源を確保することも選択肢の一つになります。ただし、本業に支障をきたさないよう、無理のない範囲で考えることが重要です。
しかし、家計見直しだけでは限界がある事例も少なくありません。根本的な借金の負担が重すぎる場合は、一時的な改善に留まってしまう可能性があります。そのような状況であれば、やはり専門家に相談して債務整理の見直しを検討することが大切だと言えます。
まとめ

任意整理後の返済が困難になった場合に行う「追加介入」は、生活状況の変化に応じて新たな債権者を任意整理に加えるために、再度交渉する手続きです。これは、当初の計画を柔軟に見直し、無理のない返済を続けるための有効な手段といえます。追加介入を行うことで、返済額の軽減や利息のカット、複数の借金の一本化などのメリットがあり、結果として返済の管理がしやすくなる点も魅力です。一方で、追加の弁護士費用や手続き期間の延長、既存の和解条件への影響といったデメリットも存在するため、慎重な判断が必要です。
追加介入を検討すべきケースとは、何らかの理由で任意整理の対象外にしていた借入先への返済が難しくなったとき、利息負担が増大しているとき、新たな借入が発覚した場合などです。こうした場合、早めに専門家へ相談し、現在の返済能力と家計状況をもとに適切な判断を行うことが重要です。
もし追加介入が難しい場合には、「個人再生」や「自己破産」への切り替えることも選択肢となります。個人再生では借金を最大10分の1まで圧縮でき、住宅を守れる可能性があります。一方、自己破産では全ての借金が免除される反面、財産の処分や一定期間の資格制限が生じます。
アヴァンス法務事務所は、独自のサービスである「アヴァンス・アシスト」で月々の返済を管理し、完済まであなたをサポートします。大切なのは、一人で悩み続けるのではなく、できるだけ早い段階で専門家に相談することです。土日を問わず24時間、全国から電話やメールでの無料相談を受付しています。まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問

Q1.信用情報(ブラックリスト)への影響は?
追加介入による信用情報への影響は、多くの方が心配されます。結論から言うと、すでに任意整理を行っている場合、追加で債権者を含めても信用情報の状況が大きく悪化することは基本的にありません。この期間は、新たなクレジットカードやローンの審査が厳しくなります。
任意整理を開始した時点で、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)にはすでに「債務整理」の情報が登録されています。この記録は通常、完済から5年間保持されますから、追加介入によって新たに「悪い情報」が加わるわけではありません。むしろ、追加介入せずに延滞を重ねてしまう方が、信用情報に「延滞」の記録が追加され、将来の回復により長い時間がかかる可能性もあるでしょう。
ただし、追加介入した債権者との和解成立時期によっては、全体の完済時期が延びることがあります。たとえば、最初の任意整理が2024年に完済予定だったとしても、追加介入によって2026年まで延びれば、信用情報の回復も2031年まで延びることになるでしょう。この点は事前に専門家とよく相談し、将来的な計画も含めて検討することが大切です。
また、追加介入する債権者が信販会社やクレジットカード会社の場合、そのグループ会社では独自の記録(社内ブラック)が長期間残る可能性があります。将来的にそれらの会社で新規の契約が難しくなることも想定しておく必要があるでしょう。
Q2.追加介入の費用相場と期間はどのくらい?
追加介入にかかる費用と期間は、債権者数や借金(債務)の金額、そして依頼する専門家によって大きく異なります。一般的な相場と流れを把握しておくことで、資金計画を立てやすくなります。
費用面では、弁護士の場合、追加1社あたり2〜5万円程度が相場です。司法書士の場合は少し安く、1〜3万円程度のケースが多いでしょう。ただし、すでに継続的に依頼している専門家であれば、初回よりも割引された料金設定になることもあります。借金が高額な場合は成功報酬が加算されることもありますから、事前に料金体系を明確に確認しておくことが重要です。
手続きの期間については、通常2〜4ヶ月程度かかります。まず専門家が追加する債権者に受任通知を送付し、取引履歴の開示を求めます。その後、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、債権者との交渉に入る、という流れです。既存の任意整理と並行して進めるため、交渉相手の債権者の方針や繁忙期によっては、さらに時間がかかる場合もあるでしょう。
注意すべきは、追加介入している間も、既存の和解に基づく返済は続ける必要がある点です。つまり、一時的に支払い負担が重くなる可能性も出てきます。この期間の資金繰りについても、事前にしっかり計画を立てておくことが必要でしょう。また、追加介入が成立すれば、全体の返済計画を見直して、月々の支払い額を調整できる場合もありますから、専門家とよく相談しながら進めることが大切です。