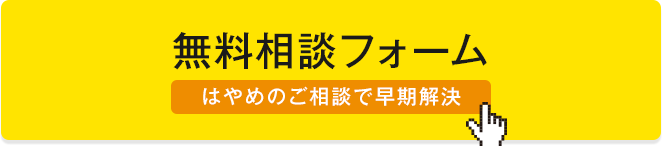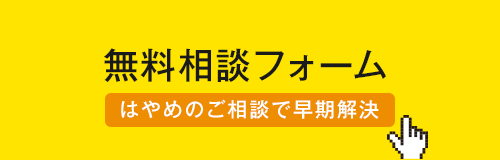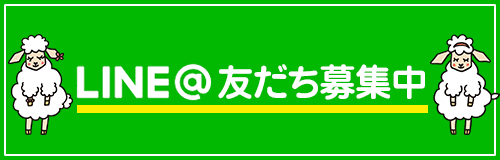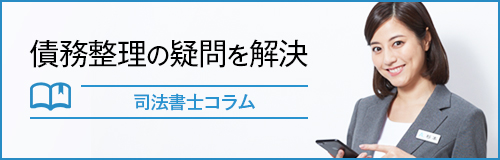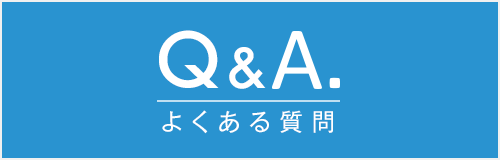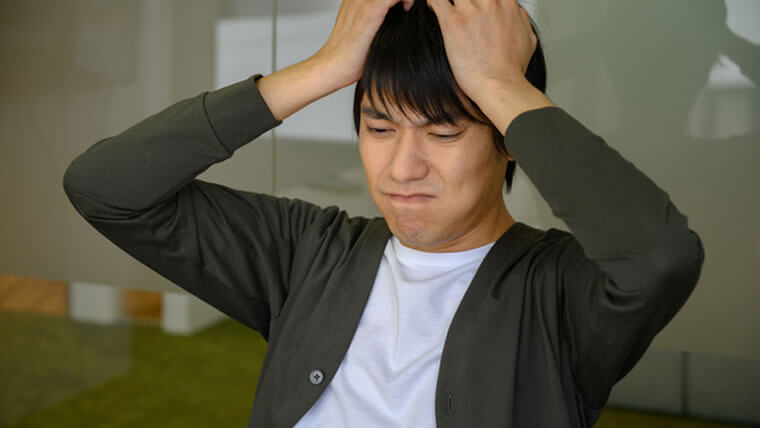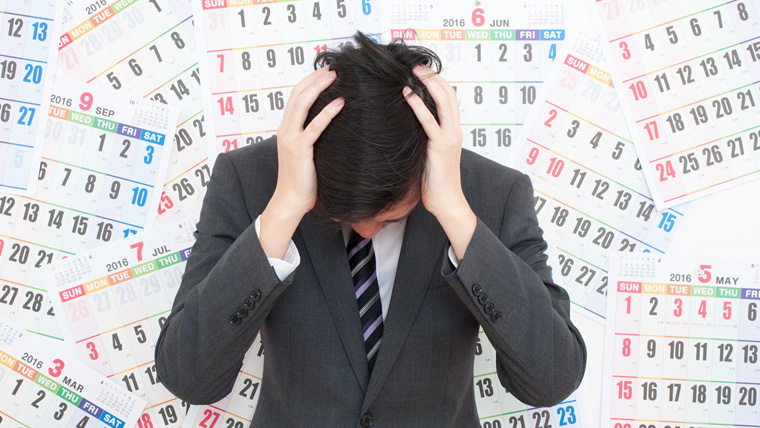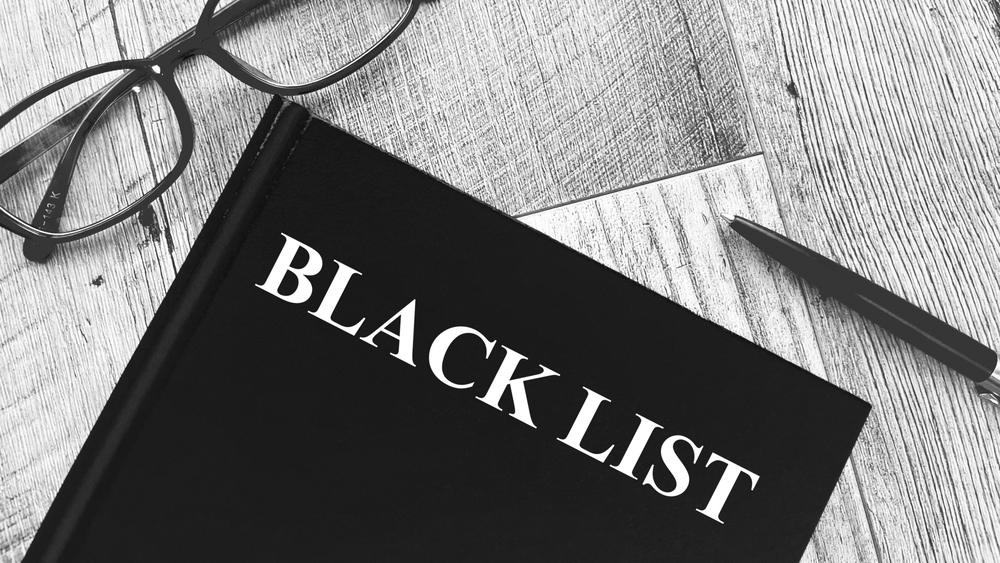2025.10.06
任意整理
複数社に借金があっても任意整理(債務整理)できる?法律事務所が相談可能か解説

複数の借入先に借金があり、返済に追われ、不安に感じていませんか。すでに多重債務に陥っている場合でも、司法書士の対応による任意整理は十分に可能です。ただし、弁護士との違いを正しく理解し、ご自身に合った専門家を選ぶことが、解決への大切な一歩になります。
この記事では、複数社に借金がある場合の任意整理について、その手続きの流れや注意点、司法書士と弁護士のどちらに依頼するべきなのかを解説します。月々の返済に悩み、苦しい状況にある方は、ぜひ参考にしてください。
複数社の任意整理は司法書士でも対応可能!基礎知識と流れ

複数の借入先からの返済に追われ、不安に感じていませんか。実は、司法書士でも複数社から借入がある場合の任意整理は十分に可能です。ここでは、司法書士に依頼できる範囲や手続きの流れ、弁護士との違いについて詳しく解説します。
任意整理とは?司法書士ができること・できないことを解説
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者(貸金業者)と直接交渉し、返済条件を見直す債務整理の方法です。具体的には、将来利息のカットや月々の返済額の減額などを求めて、3〜5年程度での完済を目指します。借金の負担を軽減し、生活再建を図るための有効な手段の一つといえるでしょう。
司法書士が任意整理で対応できる範囲には、法的な制限があります。まず、「1社あたりの債務額が140万円以下」の案件に限られます。これは司法書士法で定められた上限であり、この金額を超える場合は弁護士でなければ代理交渉を行えません。
しかし、140万円以下という制限があっても、司法書士の役割は決して小さくありません。債権者との交渉、和解契約書の作成、返済計画の立案など、任意整理に必要な手続きの大部分を担当することができます。また、司法書士は登記や法的な書類作成のプロですから、契約書類の精査や法的なリスクを把握する意味でも、その専門的な知識を持ってあなたをサポートします。
一方で、司法書士が対応できないことは、140万円を超える債務についての代理交渉と、簡易裁判所を超える裁判手続きです。もし任意整理の交渉が決裂し、訴訟に発展した場合、地方裁判所での手続きは司法書士では対応できません。ただし、任意整理は基本的に裁判外での解決を目指す手続きですので、この制限が問題になることは比較的稀なケースです。
複数社からの借金も司法書士で任意整理できる理由
「複数の会社から借りているから司法書士では無理かもしれない」と考える方もいらっしゃいます。しかし、実はそうではありません。重要なのは借入先の数ではなく、各社ごとの債務額が140万円以下かどうか、という点です。
例えば、A社から80万円、B社から100万円、C社から120万円と、合計3社から300万円を借りている場合を考えてみましょう。このケースでは、各社の債務額がすべて140万円以下です。そのため、司法書士でも十分に対応可能となります。むしろ、複数社への対応は司法書士の得意分野の一つとも言えるでしょう。
司法書士が複数社の任意整理を効果的に進められる理由として、まず事務処理能力の高さが挙げられます。各社ごとに取引履歴の取り寄せ、利息制限法による引き直し計算、返済条件の交渉といった作業を並行して進める必要がありますが、多くの司法書士事務所はこのような事務処理に長けているのです。
また、費用面でのメリットも大きいです。一般的に司法書士への依頼費用は弁護士よりも低く設定されているため、複数社への任意整理でもトータルコストを抑えやすくなるでしょう。特に、各社の債務額がそれほど大きくない場合は、司法書士への依頼が経済的負担を軽減できる可能性が高い傾向にあります。
弁護士と司法書士の違い・どちらに依頼すべき?
弁護士と司法書士の最大の違いは、扱える債務額の上限と対応できる手続きの範囲にあります。弁護士には債務額の制限がなく、個人再生や自己破産といったすべての債務整理手続きに対応できる専門家です。一方、司法書士は先述の通り140万円の制限があり、簡易裁判所の範囲内での業務に限定される、という違いがあります。
では、ご自身の状況ではどちらに依頼すべきでしょうか。判断のポイントは次のようなものです。
【弁護士】
・対応できる債務額:制限なし
・対応業務の範囲
任意整理、個人再生、自己破産など、すべての債務整理に対応
裁判所での代理人業務全般が可能
・費用の傾向:司法書士より高額な傾向
・おすすめの人
1社でも140万円を超える借金がある方
個人再生・自己破産を検討している方
複雑な案件を抱えている方
【司法書士】
・対応できる債務額:1社あたり140万円以下
・対応業務の範囲
任意整理
簡易裁判所での訴訟代理人
書類作成支援
・費用の傾向:弁護士より低額な傾向
・おすすめの人
各社の借金が140万円以下の方
費用を抑えたい方
まず、すべての借入先で債務額が140万円以下であれば、司法書士でも弁護士でも対応可能です。この場合は費用や専門家との相性を基準に選択できます。しかし、1社でも140万円を超える債務がある場合は、弁護士に依頼する必要があります。
次に、将来的な手続きの可能性も考慮しましょう。任意整理だけで解決できそうなら司法書士でも十分かもしれません。しかし、もし収入状況や債務総額を考え、個人再生や自己破産も視野に入れる必要があるなら、最初から弁護士に相談した方がスムーズに進むでしょう。後から別の専門家に改めて依頼するのは、時間的にも費用的にも負担が大きくなってしまうものです。
費用面では、一般的に司法書士の方が低額に設定されています。ただし、安さだけで選ぶのではなく、事務所の実績や対応の質も重視することが大切です。無料相談を積極的に活用し、実際に話してみてからご自身に合う専門家を見つけてください。
任意整理の一般的な流れと手続きの期間
任意整理の手続きは、大きく分けて4つのステップで進行します。全体の期間は約3〜6ヶ月程度が一般的です。ただし、債権者の数や交渉の難易度によって変動する可能性があります。
第1段階:相談・契約(1〜2週間)
まず司法書士との面談で、現在の借入状況を詳しく説明してください。任意整理がご自身にとって適切な解決方法かどうかを検討する、大切なものです。この段階で、各社の借入額、返済状況、収入状況などを整理し、今後の方針を決定します。契約が成立すると、司法書士から各債権者に受任通知が送付され、これにより取り立てが停止します。精神的な負担が大きく軽減されることでしょう。
第2段階:取引履歴の取り寄せと債務調査(1〜2ヶ月)
各債権者から過去の取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいて正確な債務額を計算し直します。過払い金が発生している場合は、この段階で判明します。複数社がある場合は、すべての債権者から資料を取り寄せる必要があるため、この期間が最も時間がかかることが予想されます。
第3段階:交渉・和解(1〜3ヶ月)
正確な債務額が確定したら、いよいよ各債権者との交渉に入ります。将来利息のカット、返済期間の延長、月々の返済額の調整などを求めて話し合いを進める段階です。債権者によって対応が異なるため、複数社の場合は個別に交渉を進める必要があります。すべての債権者と和解が成立したら、和解契約書を作成します。
第4段階:返済開始
和解契約に基づき、新しい条件での返済がスタートします。通常は翌月から返済が始まり、3〜5年間継続します。司法書士によっては、返済代行サービスを提供している場合もあり、複数社への振り込み手続きを一本化できることもありますから、確認してみると良いでしょう。
複数社への任意整理だからといって、手続きが極端に複雑になるわけではありません。ただし、各社ごとに異なる対応が必要となるため、経験豊富な司法書士に依頼することが成功の鍵を握ります。もし現在の返済状況に不安を感じているなら、一人で抱え込まずに専門家に相談することをおすすめします。
複数社の任意整理で知っておくべきリスクと失敗を回避する方法

複数社から借入がある状況で任意整理を検討されている場合、やはり単一の借入先とは異なるリスクや注意点があるといえます。特に、すべての貸金業者が任意整理に応じてくれるわけではなく、対応を間違えると返済負担がかえって重くなってしまう可能性もあります。ここでは、複数社の任意整理をする場合に、知っておくべきリスクと、それを回避する方法について解説します。
任意整理を拒否する貸金業者の特徴
任意整理は裁判所を通さない私的な交渉です。そのため、貸金業者側が交渉に応じる法的な義務はありません。一部の業者は任意整理の申し出を拒否するケースもあります。
特に拒否されやすいのは、貸付期間が短い業者です。借入から半年〜1年程度しか経過していない場合、「まだ十分な利息を回収できていない」と判断され、交渉に応じてもらえないことが多く見られます。また、既に延滞が長期間続いている業者も、「任意整理では回収できない」として拒否する傾向があります。
消費者金融系の業者の中でも、規模の小さな業者や債権回収会社に債権譲渡された案件では、任意整理よりも一括返済や法的手続きを求めることも少なくありません。これは、少額の分割払いよりも、まとまった金額を早期に回収したいという事業戦略によるものです。
さらに、過去に同じ業者で任意整理を行った履歴がある場合も要注意です。「前回も約束を守れなかった」という印象を持たれ、今回の交渉が難航する可能性が高くなります。このような業者の特徴を事前に把握しておくことは、無駄な時間や労力を避けて、交渉戦略を立てるためにも重要です。
一部の業者だけ任意整理する場合の3つの注意点
複数社からの借入がある場合、すべての業者を対象にするのではなく、一部の業者のみ任意整理を行うという選択肢もあるかもしれません。しかし、この方法には特有のリスクが存在します。注意すべき点を3つ見ていきましょう。
注意点①:対象外業者への返済負担が重くなる
任意整理を行わない業者への返済は従来通り続けなければなりません。任意整理により月々の返済額が減った分、家計に余裕ができたと錯覚してしまうケースもあるでしょう。しかし実際には、対象外にした業者への返済が相対的に大きな負担となり、結果的に延滞を起こしてしまう危険性があるのです。
注意点②:債権者平等の原則に反する可能性
特に個人再生や自己破産を将来検討する可能性がある場合、特定の債権者だけを優遇して返済していたことが問題視される場合があります。親族や知人からの借金を除き、貸金業者間で扱いに差をつけることは、後々の法的手続きに影響を与える可能性があることを知っておきましょう。
注意点③:信用情報への影響の複雑化
任意整理を行った業者の情報は「債務整理」として記録されますが、対象外業者については通常の取引として扱われます。そのため、信用情報上で一貫性のない状況が生まれ、将来の借入審査時に説明が困難になることもあるかもしれません。
これらの注意点を踏まえ、一部業者のみの任意整理を検討する際は、全体的な返済計画と将来の見通しを十分に検討することが非常に重要となります。
複数社の任意整理でよくある失敗パターンと対処法
複数社を対象とした任意整理では、単一業者の場合とは異なる失敗パターンが見られます。最も多いのは、交渉時期のズレによる失敗です。
各業者との交渉開始時期がバラバラになると、一部の業者からの督促や法的手続きが続き、精神的な負担が長期間継続してしまうことがあります。例えば、A社との交渉が成立してホッとしている間に、B社から一括返済の請求が届く、といった状況です。これを避けるためには、専門家を通じて同時期にすべての業者へ受任通知を送付し、交渉の開始タイミングを統一することが重要になります。
また、返済額の計算ミスも、失敗する理由としては深刻なものです。複数社分の返済額を合計すると、当初想定していた金額を大幅に上回ってしまい、結果的に和解後の返済が困難になるケースが頻発しています。特に、生活費の見積もりが甘く、実際の返済開始後に家計が破綻してしまう事例は少なくありません。
さらに、業者ごとの交渉結果にバラつきが生じることも問題です。ある業者は3年分割に応じてくれたのに、別の業者は1年でしか合意してくれない場合、毎月の返済スケジュールが複雑になり、管理が難しくなります。これらの失敗を回避するためにも、事前に綿密な返済計画を作成し、交渉全体を統括できる専門家に依頼することをおすすめします。個人で複数業者との交渉を同時進行させることは、時間的にも精神的にも大きな負担となるため、専門家のサポートを受けながら進めることが成功への近道といえます。
司法書士に依頼する場合のデメリットと限界
任意整理を専門家に依頼する際、費用面から司法書士を選択される方も多いことでしょう。しかし、複数社の場合には特有のデメリットがあることも理解しておく必要があります。
最も大きな制約は、1社あたり140万円以下の案件しか取り扱えないことです。 複数社からの借入総額ではなく、各社個別の債務額が基準となるため、もし1社でも140万円を超える借入がある場合は、その業者については弁護士に依頼する必要が生じます。これにより、複数の専門家に依頼することになり、かえって費用が高くついたり、手続きが煩雑になったりする可能性もあります。
また、交渉が難航した場合の対応力にも限界があります。任意整理が不調に終わり、個人再生や自己破産を検討する必要が生じた際、司法書士は代理人として裁判所での手続きを行えません。書類作成支援は可能ですが、本人が裁判所に出向いて説明や質疑応答を行う必要があり、手続きが複雑化してしまう点がデメリットです。
さらに、複数社との交渉において一部業者が訴訟を提起してきた場合、司法書士は簡易裁判所でのみ代理が可能です。地方裁判所での訴訟については本人対応となるため、法的な知識がない状態で裁判に臨むことになり、非常に不利な状況に置かれる可能性もありますから、注意が必要です。
ただし、すべてのケースで司法書士が不適切というわけではありません。各社の債務額が比較的少額で、交渉が円滑に進むと予想される場合は、やはり費用面でメリットがあるでしょう。重要なのは、ご自身の状況を正確に把握し、将来的なリスクも含めて最適な選択をすることです。
複数社の任意整理は、想像以上に複雑で専門的な知識が求められる手続きです。状況に応じた適切な選択肢を見つけるためにも、まずは経験豊富な専門家に相談し、ご自身に最も適した方法を検討されることをおすすめします。
司法書士事務所の費用相場と失敗しない事務所選び

複数の借入先から借金を抱えて返済に困っている状況では、専門家に依頼する費用も大きな判断材料となります。司法書士と弁護士では料金体系や対応範囲に違いがありますから、ご自身の状況に最も適した選択をすることで、費用対効果が高くなります。また、事務所選びで失敗してしまうと、期待した結果が得られないだけでなく、貴重な時間と費用を無駄にしてしまう可能性も否定できません。
司法書士の任意整理費用と弁護士との料金比較
司法書士の任意整理費用は、一般的に着手金が1社あたり2万円〜4万円、減額報酬が減額分の10%程度が相場です。これに対して弁護士の場合は、着手金が1社あたり3万円〜5万円、減額報酬も10%〜20%と幅があるため、複数社の借入がある場合は総額で10万円以上の差が生じることも珍しくありません。
例えば、5社の借入先に対して任意整理を行う場合を考えてみましょう。司法書士であれば着手金が10万円〜20万円程度で済むところ、弁護士では15万円〜25万円程度かかる計算になります。ただし、司法書士は借入額が1社140万円以下の案件しか取り扱えない法的制限がありますから、高額な借入がある場合は必然的に弁護士への依頼が必要です。
また、費用の支払い方法も重要なポイントです。多くの司法書士事務所では分割払いに対応しており、月々1万円〜2万円程度の支払いプランを用意しています。現在の返済負担を軽減しながら専門家費用を支払えるため、手持ち資金が少ない状況でも依頼しやすい環境が整っていると言えるでしょう。実際に相談する際は、総額だけでなく支払い方法や期間についても詳しく確認することが大切です。
複数社対応の実績豊富な事務所を見極める4つのポイント
複数の借入先を同時に整理する場合、事務所の実績と対応力が結果を大きく左右します。信頼できる事務所を見極めるための4つのポイントをご紹介します。
1. 年間の任意整理取扱件数
月に50件以上、年間500件以上の実績がある事務所であれば、さまざまなケースに対応した経験とノウハウを持っていると考えられます。ホームページや相談時に具体的な数字を確認してみましょう。
2. 債権者との交渉実績
特にあなたが借入している会社との交渉経験があるかどうかは重要な判断材料です。消費者金融や信販会社によって交渉の特徴や和解条件が異なりますので、該当する債権者との交渉を多数手がけている事務所の方が、有利な条件を引き出せる可能性が高まります。
3. 複数社対応時の管理体制
3社以上の借入先がある場合、それぞれの進捗状況を適切に管理し、依頼者に定期的な報告を行える体制が整っているかが重要です。担当制を敷いている事務所や、進捗管理システムを導入している事務所であれば、スムーズな手続きが期待できるでしょう。
4. 相談時の対応の質
あなたの状況を丁寧にヒアリングし、複数の解決方法を提示してくれる事務所は信頼できる指標の一つです。また、リスクやデメリットについても包み隠さず説明してくれる誠実さがあるかどうかも、長期的な信頼関係を築く上で欠かせない要素となります。
無料相談から正式依頼までの流れと準備すべき書類
無料相談を効果的に活用するためには、事前の準備が重要です。まず、現在の借入状況を整理した一覧表を作成しましょう。借入先の会社名、借入残高、月々の返済額、金利、契約開始時期をまとめておくと、相談時により具体的なアドバイスを受けられます。また、毎月の収入と支出も大まかに把握しておくと、返済計画の相談もスムーズに進むでしょう。
相談当日に持参すべき書類として、各借入先からの請求書や契約書、給与明細書3か月分程度があると理想的です。書類が手元にない場合でも相談は可能ですので、準備できない書類があっても遠慮せずに相談してください。多くの司法書士事務所では、必要書類の取得方法についても丁寧にアドバイスしてくれます。
無料相談では通常30分〜1時間程度の時間で、あなたの状況に最適な解決方法を提案してもらえます。任意整理以外にも個人再生や自己破産といった選択肢がある場合は、それぞれのメリット・デメリットを比較検討することになるでしょう。相談後すぐに決断する必要はありません。自宅でゆっくり検討してから後日連絡する形でも全く問題ありませんので、ご安心ください。
正式依頼を決断した場合は、委任契約書の締結と着手金の支払いを行います。契約後は司法書士が債権者に受任通知を送付し、これにより取り立てが停止されます。この段階で精神的な負担が大幅に軽減されるため、多くの依頼者にとって大きな安心感を得られることでしょう。
初回相談で必ず確認すべき質問チェックリスト
初回相談を有効活用するために、事前に質問項目を整理しておくことをおすすめします。ぜひ以下のチェックリストを参考に、疑問を解消してください。
・費用について
☑ 総額でいくらかかりますか?
☑ 分割払いは可能ですか?
☑ 追加費用が発生する可能性はありますか?(特に複数社対応の場合の費用体系)
・手続きの進行について
☑ 完了までの期間はどれくらいですか?
☑ 進捗報告の頻度と方法を教えてください。
☑ 債権者からの連絡は完全に止まりますか?
・事務所の実績・見通しについて
☑ この事務所での類似ケースの実績はありますか?
☑ 私のケースで予想される和解条件を教えてください。
☑ 手続き中に特に注意すべき点は何ですか?
・手続き完了後のサポートについて
☑ 任意整理後の返済管理についてサポートはありますか?
☑ 将来的に返済が困難になった場合の相談対応は可能ですか?
借金問題は一人で抱え込まずに、専門家の力を借りることで必ず道筋が見えてきます。アヴァンス法務事務所では、土日・休日を問わず24時間、全国からメールや電話での相談を受付しています。また、「アヴァンス・アシスト」という独自のサービスで、複数社から借入がある場合でも、完済まであなたをサポートいたします。まずはお早めに、ご相談ください。
まとめ

借金の返済に悩んでいる方にとって、任意整理は重要な選択肢の一つです。しかし、メリットだけでなくデメリットも理解した上で慎重に判断することが大切になります。
任意整理のメリットは、将来利息のカットや返済計画の見直しにより、月々の負担を軽減できる可能性があることです。また、裁判所を通さない手続きのため比較的プライバシーが保たれます。手続き期間中の督促が止まることで、精神的な負担が軽減されることも大きな利点です。一方で、信用情報機関への登録により約5年間は新たな借入やクレジットカードの作成が困難になるデメリットもあります。対象とする債権者を選択できるものの、全ての債務者に対して確実に減額が実現するわけではありません。そして、毎月の返済は継続する必要がある、といった注意すべき点も多数存在します。
特に重要なのは、任意整理を行った後も安定した収入を維持し、決められた返済を継続していく必要があるということです。手続きを行ったからといって借金がゼロになるわけではありません。むしろ新たな返済計画に基づいて、確実に支払いを続けていく責任が生じます。この点を十分に理解せずに任意整理を選択してしまうと、後々さらに困難な状況に陥る可能性もありますから、注意深く検討しましょう。
また、任意整理は債権者との交渉によって成立する手続きのため、必ずしも希望通りの条件で合意に至るとは限りません。債権者によっては交渉に応じない場合もあるため、提示される条件が期待していたものと異なる場合もあるかもしれません。このような状況を避けるためには、事前に十分な準備と情報収集を行うことが不可欠です。
さらに、任意整理以外の債務整理方法との比較検討も重要です。個人再生や自己破産といった他の選択肢についても理解を深め、ご自身の状況に最も適した方法を選択することが大切になります。それぞれの手続きには異なるメリット・デメリットがあり、収入状況や借金の総額、保有している財産などによって最適な選択肢は変わってくるからです。
こうした複雑な判断を一人で行うのは非常に困難なことでしょう。借金問題に詳しい弁護士や司法書士に相談することで、ご自身の状況を客観的に分析してもらい、最適な解決方法を見つけることができます。また、専門家に依頼することで手続きの負担も大幅に軽減されます。債権者との交渉から書類の作成まで、煩雑な手続きを代行してもらえるため、あなた自身は新しい生活の準備に集中できるでしょう。
アヴァンス法務事務所に依頼される方の約8割は任意整理による借金の解決を選択されます。借金問題は、時間が経過すればするほど、選択肢が狭まってしまうことも考えられます。まずはお気軽にご相談ください。