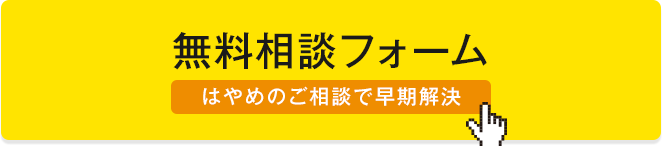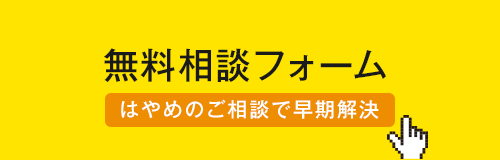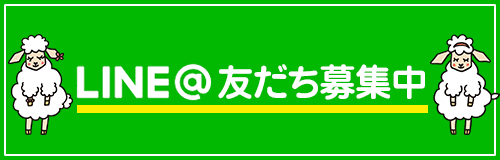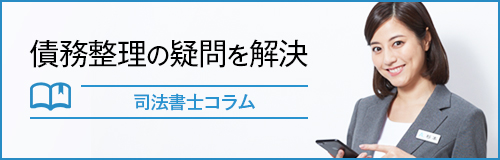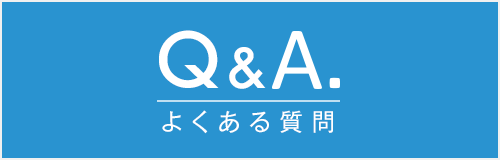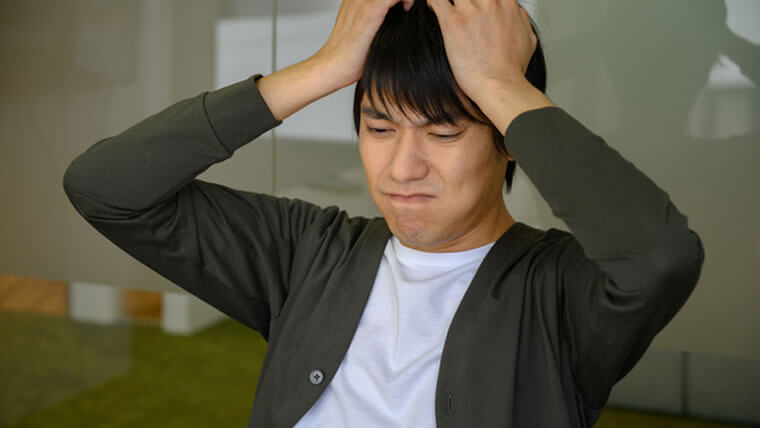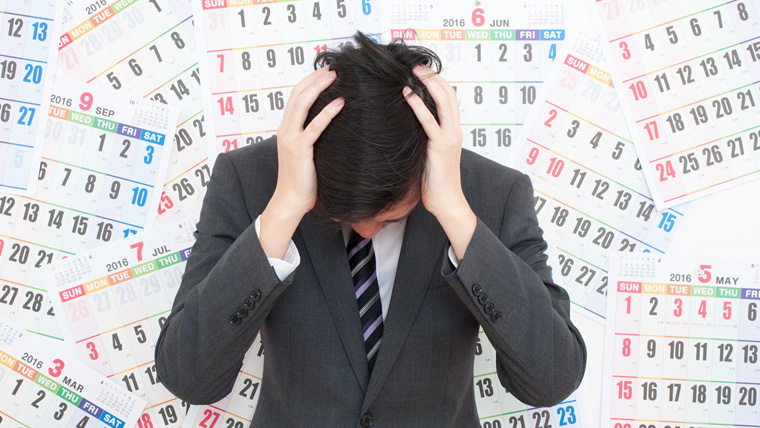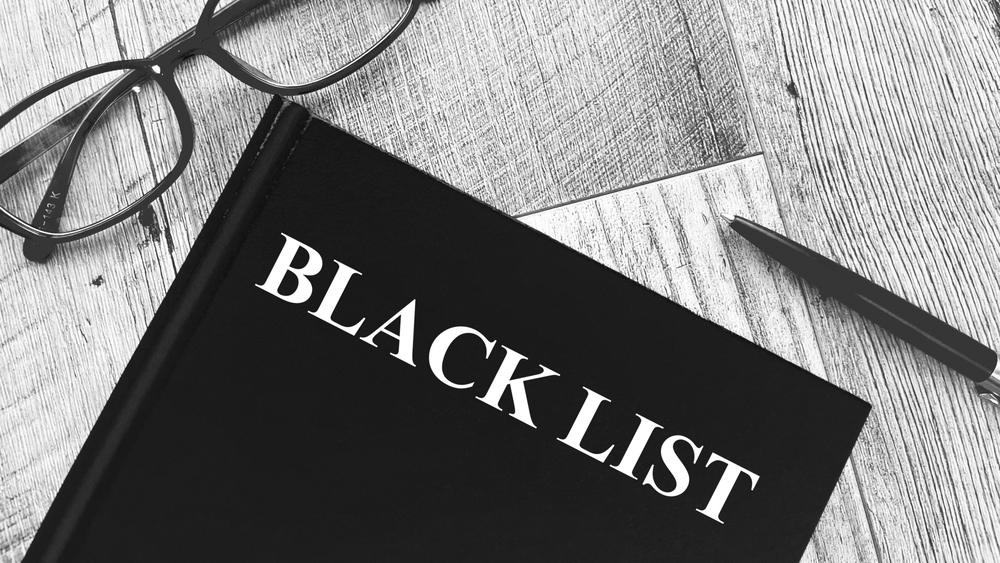2025.09.29
任意整理
任意整理(債務整理)で持ち家は残せる?住宅ローンを含む条件も解説

借金の返済に悩み、任意整理を検討している方は、「任意整理をしたら家を失ってしまうのではないか」という不安な気持ちがあるかもしれません。特に、住宅ローンを抱えている方にとっては、切実な問題だと思います。
結論から申し上げますと、任意整理では基本的に持ち家を手放す必要はありません。任意整理は、債務整理の中でも特に柔軟性の高い手続きです。そのため、住宅ローンが残っている持ち家でも、そのまま持ち続けることが可能です。これは任意整理の大きなメリットの一つといえるでしょう。
この記事では、任意整理で持ち家を残せる、その理由と住宅ローンとの関係について解説します。
任意整理は持ち家を手放さずに済むのか?

任意整理では、どの債権者と交渉するかを債務者自身で選ぶことができます。つまり、住宅ローンを組んでいる金融機関は対象から外し、クレジットカード会社や消費者金融からの借金だけを整理対象にできるのです。この仕組みを理解すると、なぜ家を守れるのかが分かります。
つまり、住宅ローンの支払いをこれまで通り続けながら、他の借金の返済負担を軽減できるわけです。実際に多くの方が、住宅ローンを除く借金について、月々の返済額を減らしたり、将来の利息をカットしたりすることで、家計の立て直しを図っています。
持ち家を残せる基本条件
持ち家を維持しながら任意整理を進めるためには、いくつかの基本的な条件をクリアする必要があります。
まず最も重要な条件は、住宅ローンの返済を継続できる経済力があることです。具体的には、任意整理後の返済額(住宅ローンと、整理した借金の分割返済分を合わせた額)が、月収の3分の1以下に収まることが一つの目安とされています。例えば、月収30万円の方でしたら、合計返済額が月10万円以下であることが望ましいでしょう。
次に、住宅ローンの返済に遅延がないことも重要な条件です。もしすでに住宅ローンの滞納が続いている場合、任意整理をしたとしても、住宅ローン債権者から競売や任意売却を求められる可能性が出てきます。このような状況では、個人再生の「住宅資金特別条項」の利用を検討する方が良いケースもあることを知っておいてください。
また、住宅ローン以外の借金が住宅を担保にしていないことも必要条件の一つです。もし消費者金融などが住宅に根抵当権を設定している場合、任意整理だけでは解決が難しくなることもあります。
さらに、任意整理後の返済計画に現実性があることも欠かせません。単に月々の返済額が減るだけでなく、家計全体の収支バランスが改善し、継続的な返済が可能な状況を作り出せるかが問われます。生活費の見直しや収入増加の見込みなども含めて、総合的な判断が求められるところです。
任意整理後も住宅ローンの返済は、これまでと変わらず継続しなければなりません。そのため、任意整理後の返済能力をしっかりと見極めることが大切になります。また、住宅ローン以外の借金についても、完全にゼロになるわけではなく、通常3〜5年かけて分割で返済していくのが一般的です。
住宅ローンの返済中でも任意整理できる?
住宅ローンの返済中であっても、任意整理を行うことは十分に可能です。むしろ、住宅ローン以外の借金が重荷になっている方にとって、任意整理は持ち家を維持しながら借金問題を解決できる、有効な手段となるでしょう。
任意整理の手続きでは、住宅ローンを整理対象から除外できます。これにより、住宅ローン債権者との関係に影響を与えることなく、手続きを進めることが可能です。つまり、住宅ローンの契約内容や返済条件は変わらず、これまで通りの支払いを続けることになるわけです。この点が、すべての債務が整理対象となる自己破産や個人再生との大きな違いといえます。
実際の手続きでは、弁護士や司法書士が住宅ローン以外の債権者と個別に交渉を行います。多くの場合、将来の利息がカットされたり、返済期間が延長されたりすることで、月々の返済負担を大幅に軽減できる可能性があります。例えば、複数のクレジットカード会社に対する月10万円の返済が、任意整理によって月5万円程度まで削減されるケースも珍しくありません。ただし、住宅ローンの返済状況によっては注意が必要です。
任意整理で持ち家を失う3つのリスクと回避策

任意整理は、債務者の方にとって有効な選択肢の一つではありますが、住宅ローンがある場合には特別な注意が必要です。誤った判断や準備不足が原因で、せっかくの持ち家を手放すことになってしまうケースもあります。ここでは、そうしたリスクを3つの観点から詳しく解説し、それぞれの回避策についてもお伝えしていきます。
1.住宅ローンを任意整理に含めてしまった場合
任意整理の最も重大なリスクの一つは、住宅ローンを整理対象に含めてしまうことです。任意整理は債権者との交渉を通じて、将来の利息をカットし、元本のみを分割で返済していく手続きです。しかし、住宅ローンを含めてしまうと、残念ながら必然的に持ち家を失うことにつながります。
住宅ローンの場合、お金を借りる際に土地や建物に抵当権が設定されています。もし返済が困難になれば、金融機関は抵当権を実行して家を競売にかけることが可能になります。つまり、住宅ローンを任意整理に含めた瞬間、金融機関は「期限の利益の喪失」を宣言し、残りの住宅ローンを一括で返済するよう求めてくるでしょう。一般的に、住宅ローンの残債を一括で返済できる方はほとんどいらっしゃらないため、結果的に競売によって家を売却せざるを得なくなってしまうのです。
この状況を回避するためには、任意整理の対象を慎重に選ぶことが何よりも重要です。住宅ローンは任意整理の対象から必ず除外し、カードローンやクレジットカードなど、他の無担保債務のみを整理対象とする必要があるでしょう。例えば、消費者金融3社から合計200万円の借金があり、住宅ローン残債が2,000万円という場合でしたら、消費者金融の200万円だけを任意整理し、住宅ローンはこれまで通り返済を継続するという方針を取るのが一般的です。
ただし、この判断には専門的な知識と経験が求められます。ご自身の債務の内容や返済能力を総合的に分析し、最適な選択を行うためには、弁護士や司法書士といった法律の専門家への相談が不可欠といえるでしょう。
2.収入減少・返済困難で家を失うリスク
任意整理後に発生しやすい二つ目のリスクは、収入の減少や予期せぬ支出によって、住宅ローンの返済が困難になることです。任意整理によって他の債務負担は軽減されるものの、通常は住宅ローンの返済額は変わりません。そのため、収入基盤が不安定であったり、家計管理が十分でなかったりする場合には、結果的に住宅ローンの延滞につながってしまう可能性もあります。
具体的なケースとして、任意整理によって月々の返済負担が8万円から3万円に減ったものの、住宅ローンが月10万円残っている状況を想定してみましょう。任意整理前は総返済額が18万円でしたが、13万円になることで、月5万円の余裕が生まれます。しかし、この余裕分を生活費の向上に充てすぎてしまったり、他の支出が増加したりすると、もし何らかの収入減があった際に、住宅ローンの返済が困難になってしまうかもしれません。
さらに深刻なのは、任意整理後3〜5年程度で完了する返済計画を立てている間に、転職や病気、家族の事情などで収入が大幅に減少してしまうケースです。例えば、月収35万円で返済計画を立てていた方が、勤務先の業績悪化によって月収25万円になってしまった場合、住宅ローンの返済継続が物理的に不可能になることも考えられます。
このリスクを軽減するためには、任意整理後の家計管理を徹底し、余裕資金の一部を緊急時の備えとして蓄えておくことが重要です。また、収入の多角化や安定化に向けた取り組みも並行して行うと良いでしょう。返済計画を立てる段階で、現実的な収入見込みを基に、多少の変動があっても対応可能な計画を立てることが重要です。
3.任意整理前に準備すべき対策と相談先
持ち家を守りながら任意整理を成功させるためには、事前の準備と専門家選びが不可欠です。まず重要なのは、現在の債務状況と収支バランスを正確に把握することです。住宅ローンを除く債務の総額、月々の返済額、そして任意整理後の想定返済額を明確にし、住宅ローンを含めた総返済額が収入に対して適正な範囲に収まるかどうかを慎重に検証する必要があります。
家計の見直しも、同時並行で進めるべき大切な対策の一つです。食費や光熱費、通信費、保険料といった固定費を見直し、住宅ローン返済を継続するための財政基盤を強化することが求められます。例えば、格安SIMへの変更で通信費を月5,000円削減したり、保険の見直しで月3,000円の節約を実現したりすることで、年間10万円近い支出削減が可能になることもあります。
また、任意整理の手続きを進める前に、住宅ローンの借入先である金融機関との関係性も整理しておくべきでしょう。もし同一の金融機関でカードローンなど他の借り入れがある場合、任意整理によって全体の取引関係に影響が出る可能性があります。こうした複雑な状況を避けるためにも、債務整理に詳しい弁護士や司法書士に早めに相談し、総合的な戦略を立てることが重要です。
任意整理のメリット・デメリット

任意整理は債務整理の中でも比較的負担の少ない手続きとして知られていますが、メリットだけでなくデメリットも存在します。特に住宅ローンがある方の場合、マイホームへの影響や今後の生活設計への影響を慎重に検討しなければなりません。
ここでは、任意整理の具体的なメリットとデメリットを整理し、よくある誤解についても解説していきます。
任意整理を選択するメリット
任意整理の最大のメリットは、住宅ローンを除外して手続きできる点です。これは、住宅ローン支払い中の方にとって非常に重要な特徴といえるでしょう。自己破産や個人再生とは異なり、任意整理では債権者を選んで交渉できるため、住宅ローンはそのまま継続し、消費者金融やクレジットカードの借金だけを整理対象にすることが可能なのです。
・住宅ローンを維持できる:住宅ローンを整理対象から外せるため、マイホームを手放さずに済む。
・将来利息のカット:債権者との交渉で、今後発生する予定の利息を減らせる可能性が高い。
・月々の返済負担を軽減:利息減や返済期間の延長により、毎月の支払いを大きく下げられる。例として、月80万円が月3〜4万円になる場合がある。
・裁判所を通さない手続き:自己破産や個人再生と異なり、裁判所での複雑な手続きが不要。
・家族や職場に知られにくい:私的な交渉で官報掲載がなく、周囲に借金問題が広がりにくい。
・財産の処分が不要:自動車や生命保険、退職金、不動産などの財産を手放す必要がない。
・取り立てが止まる:弁護士や司法書士に依頼すると、債権者からの督促が速やかに停止する。
任意整理のデメリットとよくある誤解
一方で、任意整理にはいくつかのデメリットも存在します。最も大きな影響は信用情報機関への登録(いわゆるブラックリスト)でしょう。
・信用情報への登録:任意整理を行うと事故情報が登録され、約5年間は新規クレジットカードの作成や住宅ローン・自動車ローンなどの利用が難しくなる。
・元金の減額は期待しにくい:交渉の中心は将来利息のカットや返済期間の延長であり、元金が大きく減るケースは稀。ネットの「大幅減額」は過払い金がある特殊例を除けば誤解が多い。
・債権者が交渉に応じない可能性:任意の交渉であるため、条件を拒否されることがある。借入期間が短い場合や延滞を繰り返している場合は協力が得にくい。
・専門家の費用が発生:弁護士や司法書士に依頼すると着手金や成功報酬などで数十万円程度かかることが一般的。分割払い対応もあるが、軽減される金額とのバランスを検討する必要がある。
これらのメリット・デメリットを総合的に判断するためには、ご自身の具体的な状況を専門家に相談することが最も確実な方法です。借金の総額、収入状況、住宅ローンの残高などを踏まえて、任意整理が本当に最適な選択肢なのか、それとも他の方法を検討すべきなのかを判断してもらうことができます。
任意整理の手続き方法と持ち家への影響を詳しく解説
.jpg)
住宅ローンを支払い中で借金返済に困っている方にとって、任意整理は持ち家を守りながら債務を整理できる可能性がある方法です。ただし、手続きや住宅ローンへの影響について正しく理解することが重要になります。ここでは、手続きの流れとその影響についてご紹介します。
任意整理の具体的な流れ(必要書類・期間・費用)
任意整理の手続きは、弁護士や司法書士に依頼して、債権者との間で返済条件を見直す交渉を行うのが一般的です。具体的な流れをステップごとに見ていきましょう。
1.専門家への相談と契約
まずは債務整理に詳しい弁護士や司法書士に相談し、ご自身の状況に任意整理が適しているかを判断してもらいます。内容に納得できれば、委任契約を結ぶことになります。
2.受任通知の送付
専門家が各債権者に対して受任通知(弁護士・司法書士が代理人になったことを知らせる書面)を送付します。この受任通知が届くと、債権者からの直接的な督促や取り立ては一時的に停止されます。
3.取引履歴の開示請求と引き直し計算
専門家が債権者からこれまでの取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいた正確な借金の残高(元金)を計算し直します。
4.債権者との交渉
引き直し計算で確定した借金(元金)を基に、専門家が債権者と交渉を開始します。主に将来利息のカットや、無理のない範囲での分割返済(通常3~5年)の合意を目指します。住宅ローンは交渉対象から除外されます。
5.和解契約の締結と返済開始
交渉が成立すれば、債権者と専門家の間で和解契約書を締結します。その後、新しい返済計画に基づいて、専門家の口座などを経由して各債権者への返済をスタートします。
【必要な書類】
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・各債権者との契約書や借用書、直近の取引明細書
・給与明細書や源泉徴収票といった収入証明書類
・家計収支表
・住宅ローンの返済予定表、ローン契約書、残高証明書(住宅ローンがある場合)
【手続き期間】
一般的に3~6か月程度を要します。債権者の数や債務額、交渉の難易度によって期間は変動しますが、住宅ローンがある場合は慎重な検討が必要なため、やや長期化する傾向もあります。
【費用】
・弁護士に依頼する場合: 着手金が1社あたり2~4万円程度、成功報酬が減額分の10~20%程度が相場です。
・司法書士に依頼する場合: 弁護士よりやや安く設定されていることが多いでしょう。
住宅ローン付きの複雑なケースでは弁護士への依頼が適している場合もありますので、事前に複数の専門家から見積もりを取り、費用対効果を検討することをお勧めします。
任意整理中の住宅ローン管理方法
任意整理において最も重要なポイントは、住宅ローンを整理対象から除外することです。任意整理は債務整理の中でも自由度が高く、どの債権者と交渉するかを選択できるため、住宅ローンだけは従来通り支払い続けることで持ち家を維持できます。
住宅ローンを継続的に支払うためには、任意整理によって他の借金の返済額が軽減された分を、住宅ローンの支払いや生活費の安定に充てることが大切です。例えば、クレジットカードやカードローンなどの返済額が月10万円から5万円に減額されれば、その浮いた5万円を家計に有効活用できます。ただし、住宅ローンの支払いがすでに滞っている場合は、金融機関との個別の相談が必要な場合もあります。
注意点は、任意整理中であっても住宅ローンの支払いは確実に継続する必要があることです。住宅ローンが滞納状態になると、最終的に競売にかけられるリスクがあり、結局持ち家を失うことになりかねません。そのため、任意整理で軽減される返済額と住宅ローンの支払額のバランスを慎重に検討し、無理のない返済計画を立てることが極めて重要になります。
また、住宅ローンを組んでいる金融機関に任意整理の事実が知られることを心配される方もいらっしゃいます。しかし、住宅ローンを整理対象から外している限り、基本的に金融機関に直接的な影響を与えることはありませんのでご安心ください。ただし、信用情報機関への登録によって間接的に知られる可能性は考慮しておきましょう。
任意整理完了後の信用情報と家計管理
任意整理が完了した後も、信用情報機関には事故情報として記録が残ります。この記録は一般的に完済から約5年間保持されるため、この期間中は新たなローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることが難しくなる可能性があります。住宅ローンは、既存の契約は継続されますが、借り換えや追加融資を受けることは難しくなることについて、理解が必要です。
家計管理の面では、任意整理によって返済負担が軽減されたとしても、根本的な家計の見直しが不可欠です。収入と支出のバランスを改めて整理し、住宅ローンを含めた固定費、生活費、貯蓄のバランスを適切に保つことが求められます。特に、将来の住宅修繕費や家族の教育費なども考慮した、長期的な資金計画を立てることが大切になります。
任意整理完了後は、現金中心の生活に移行される方が多くいらっしゃいます。クレジットカードが使えない期間は、デビットカードや現金での支払いをメインとし、支出を「見える化」することで家計を健全に保つことができます。また、緊急時の備えとして、少額ずつでも貯蓄を始めることをおすすめします。
他の債務整理手続きとの比較

住宅ローンがある状況で債務整理を検討する際、任意整理、個人再生、自己破産それぞれの特徴を理解しておくことは非常に重要です。どの手続きを選ぶかによって、住宅への影響や今後の返済計画が大きく変わってくるからです。
それぞれの手続きには特有のメリット・デメリットがあり、現在の借入状況や収入、将来の見通しなどを総合的に判断して選択する必要があります。特に住宅ローンについては、各手続きで取り扱いが根本的に異なるため、その違いを正確に把握することが適切な選択につながります。
個人再生の「住宅ローン特則」
個人再生の「住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)」は、大切な住宅を維持しながら、その他の借金を大幅に減額できる制度です。この特則を利用すると、住宅ローンはこれまで通り契約通りに支払い続けながら、その他の借金については元金を5分の1から10分の1程度まで圧縮することが可能になります。
任意整理との最も大きな違いは、借金の減額幅にあるでしょう。任意整理では主に将来の利息カットが中心となるため、元金そのものの減額は基本的に期待できません。一方、個人再生では裁判所の認可決定により、法律に基づいて大幅な元金カットが実現します。
ただし、個人再生を利用するためには厳格な要件がいくつかあります。継続的な収入があることはもちろん、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であること、そして減額後の借金を3年から5年で完済できる返済能力があることが求められます。また、裁判所への申立てが必要で手続きが複雑になり、官報にも掲載されるといった制約もあります。
任意整理の場合は、住宅ローンを整理対象から除外できます。そのため、住宅への直接的な影響を避けながら、クレジットカードやカードローンなどの無担保債務のみを整理できるのが特徴です。手続きも債権者との直接交渉が中心で、裁判所を通さないため比較的シンプルに進められます。ただし、借金の減額効果は個人再生ほど大きくないため、返済総額を大幅に圧縮したい場合には物足りないと感じる可能性もあるでしょう。
自己破産・個人再生とのメリット・デメリット比較
自己破産は、返済不能な状況に陥ってしまった場合の最終的な選択肢として位置づけられています。免責が認められることで、原則としてすべての借金の支払い義務が免除されます。しかし、その代償として住宅などの高額な財産は処分される可能性が高いと言えます。住宅ローンが残っている場合、通常は競売や任意売却によって住宅を手放すことになります。そのため、持ち家を維持したい場合の選択肢としては、任意整理と個人再生(住宅ローン特則付き)が現実的です。
それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。
【任意整理】
・持ち家への影響:維持できる(住宅ローンを対象から除外)
・借金の減額幅:将来利息のカットが中心で元金減額は期待薄
・手続きの複雑さ:比較的シンプルで裁判所を通さない
・期間:3〜6か月程度(交渉期間)
・費用:債権者数に応じて変動し比較的安価
・信用情報:完済から約5年間登録
・家族への影響:比較的知られにくい
・職業・資格制限:なし
・財産の処分:なし
【個人再生(住宅ローン特則付き)】
・持ち家への影響:維持できる(住宅ローン特則を利用)
・借金の減額幅:元金が大幅に減額(5分の1から10分の1程度)
・手続きの複雑さ:複雑で裁判所への申立てが必要
・期間:6か月から1年程度
・費用:弁護士費用と裁判所の予納金が必要で高額になりがち
・信用情報:官報掲載後、約5〜10年間登録
・家族への影響:裁判所からの書類などで知られる可能性あり(官報掲載)
・職業・資格制限:なし
・財産の処分:なし(価値の高い財産は換価されることもある)
【自己破産】
・持ち家への影響:原則として失う(住宅などの財産を処分)
・借金の減額幅:全ての借金が免除
・手続きの複雑さ:複雑で裁判所への申立てが必要
・期間:3か月から1年程度
・費用:弁護士費用と裁判所の予納金が必要(個人再生より安価な場合もある)
・信用情報:官報掲載後、約5〜10年間登録
・家族への影響:裁判所からの書類などで知られる可能性が高い(官報掲載)
・職業・資格制限:一時的に一部の職業や資格に制限がかかる場合あり
・財産の処分:原則として高額な財産は処分される
現在の返済能力や借入総額、住宅と将来の収入見通しなどを総合的に検討し、ご自身の状況に最も適した方法を選択することが重要です。どの手続きにもメリット・デメリットがあるため、専門家に相談して客観的なアドバイスを受けることで、より適切な判断ができるようになります。法的な手続きは一度開始すると後戻りが困難な場合もあるため、十分な検討と準備を行った上で決断されることをおすすめします。
まとめ

借金問題を抱えていても、持ち家を失うことが不安で手続きに踏み切れない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、任意整理であれば、大切な住宅を手放すことなく返済負担を軽減できる可能性があり、個人再生なら住宅資金特別条項を活用して自宅を守りながら、大幅な債務圧縮が期待できる方法もあります。
重要なのは、一人で悩み続けるのではなく、早めに専門家へ相談することです。債務整理には複数の選択肢があり、あなたの収入状況、借入総額、住宅ローンの残債などによって、最適な方法は変わってきます。弁護士や司法書士といった専門家であれば、これらの要素を総合的に判断し、住宅を維持しながら返済を続けられる現実的な解決策を提案してくれるはずです。
また、債務整理を検討する際は、配偶者や家族への影響についても正しく理解しておくことが大切です。生活の見直しや今後の資金計画については、家族と話し合っておく必要があるかもしれません。一方で、多くの場合、家族が保証人になっていなければ直接的な影響は限定的です。
借金問題は、時間が経つほど解決が困難になる傾向があるものです。アヴァンス法務事務所では、ご依頼される方の約8割が任意整理による債務整理を選択されます。全国から24時間、メールや電話でのご相談を無料で受付しています。まずはお気軽にご相談ください。